シークレットストーリー
……の空気が好きだ。
誰の言葉も、視線も気にすることなく、
静かな時間に身を委ねることができる。
今日も普段通り、始業時間より早く登校し、
この場所で勉強に集中していた。
……いつもと違うのは今日が『文化祭』で、
学内全体の空気が浮ついているところだ。
校門には学外の人を歓迎する巨大な看板が立ち、
その先の敷地内には色とりどりの屋台が並んでいる。
並ぶ屋台の中には俺のクラスの店もあるはずだが、
俺は顔を出すこともなく……に入り浸っていた。
すれ違った見覚えのあるクラスメイトも何も言わない。
俺の助力などそもそも期待されていないと分かっていた。
高校へ入学してからの数か月、
俺はクラス内で浮いた存在だった。
俺には将来の目標があるし、何より人付き合いが億劫だ。
他の生徒のように学生生活を謳歌する余裕などないし、
そうなりたいとも思っていない。
ぱん、ぱんと空砲のような音が……まで聞こえる。
文化祭中は自主勉強に専念できると思ったのに……
集中力を削られた俺は、窓越しに快晴の空を眺めた。
「あんた、そんなとこにいたの?」
唐突に響く、この場所に相応しくない無遠慮な声。
―― マズいな、見つかった。
声の主は進学校であるこの学校には珍しく、
派手な金髪で、制服を着崩した同級生の女生徒。
普段から素行が悪く、皆から厄介者だと思われている。
金髪の彼女は俺と違う意味でクラスから浮いており、
そして何故か、度々俺にちょっかいを出してくる。
彼女は図々しくも俺の向かいの席に腰かけ、
けらけらと笑って「今日も勉強とかウケる」などと、
いい加減なことを言ってきた。
俺は暇ではないことを言外に示すために、
参考書に目を落として、彼女の話を受け流す。
しかし、金髪の同級生は怯みもせずに話しかけてきて、
いつも最後には俺が根負けする流れになるのだ。
残念ながら、今日も例外ではなかった。
彼女に何か用かと聞いてみると、
「一人なら、一緒に学園祭まわろうよ」と言う。
何故? 俺が? お前と??
彼女は普段通りの諦めの悪さで喚き散らし始める。
挙句の果てに、彼女は卓上にあった俺のスマホを取り上げ、
「返してほしかったら、あたしに付いてきて!」
と言いながら、……の入り口まで走って行ってしまう。
こうなっては宥める方が大変だろう……
結局「少しだけなら」という条件で文化祭を回ることにした。
その方が、結果的に早く解放されると計算しての行動だ。
俺は金髪の彼女を、会った当初は敬遠していた。
派手な姿も、一人でへらへらしている性格も相いれない。
だが、入学してからの数か月間、
俺の人間性を知ったうえで、
継続して話しかけてきたのは彼女だけだ。
そして時折会話の中から覗く、彼女の家庭環境や、
内面を知るにつれ、見る目が変わっていった。
うるさくて、面倒で、正直に言えば勉強の邪魔だ。
だけど俺は、彼女を嫌いになれなかった……
風船や紙製の花飾り、ペンキで塗った看板に彩られた校内を、
楽しそうにはしゃぐ金髪の同級生と歩く。
改めて見ると、今日の校内は特別な空気を纏っており、
綿あめを持って歩く親子連れや、着ぐるみが闊歩している。
文化祭の準備中、最低限の係の仕事以外を避けてきたが、
短い期間でここまで飾り付けられているとは驚きだ。
彼女は俺の腕をお構いなしに引っ張っていき、
『射的』の文字の書かれた看板のある教室に入った。
すると、ノリのいい生徒が家電量販店の店員ばりに
威勢よく俺達を歓迎し、割りばし製の銃を持ってくる。
俺が戸惑っていると、一回百円で五回撃てると説明し、
輪ゴムを渡された。
もたもたとゴムをセットしている間に、
がらんがらんと鈴が鳴らされる音がした。
横を見れば、ガッツポーズを取っている彼女がいる。
撃ち落とした小さなウサギのマスコットを貰い、
次のゴムをセットして獲物に狙いを定めている。
俺も負けじとじっくり的を狙い撃ってみるが……
情けないことに明後日の方向に跳んで行ってしまう。
残り一発。
せめて一つだけでも当てようと、殊更に慎重になる。
景品を袋にまとめ終えた彼女が、こちらを見ていた。
―― どうせ、内心馬鹿にして笑っているのだろう。
だが、俺の状況を把握した彼女は、
意外にも簡潔なアドバイスを述べた。
男子としてのプライドを傷つけないように、優しく丁寧に。
それはどこか俺の知っている人を思わせた。
金髪の同級生は、年の離れた弟妹を持つ長女で、
姉として面倒見のいい部分があるのかもしれない。
彼女の助言を受け、俺は改めて割りばしの銃を構える。
緊張の一瞬……しかしそう簡単に事は運ばず、
輪ゴムの弾はお菓子の箱の端を掠めて終わった。
彼女は、「惜しかったね」と笑顔で言って、
自分の袋からキャラメルの箱をこちらに投げて寄越す。
俺が受け取った時点で、既に別の教室に向かおうとしている。
「はやくはやく!」
まるで長いこと友人だったような、親しげな声。
それからも、二人で各クラスの店を巡った。
出場させられた早押しクイズ大会で俺が優勝したり、
彼女が欲しがったたこ焼きを分け合って食べたり、
その度に、彼女は嬉しそうに笑っていた。
時折やるべきことを果たしていない罪悪感が胸を焦がすも、
それは俺が想像していたよりも悪い時間じゃなかった。
展示や売店をあらかた回った頃には日も落ち始め、
流石にそろそろ……に戻る旨を金髪の同級生に告げる。
すると彼女は、文化祭の目玉である花火が見たいと言う。
曰く、毎年この学校では花火を打ち上げるらしい。
そしてよほど楽しみにしていたのか、彼女は俺を、
花火の観覧しやすい空き教室へと案内した。
教室についた途端、彼女は慌ただしくトイレに走って行った。
楽しくて行くタイミングを逃していたという彼女に、
俺はつい笑ってしまう。
『少しだけ』付き合うつもりだったはずが、
教室の時計を見ると、もうこんな時間だ……
騒々しいのも、人に構われるのも苦手だが、
けれど ―― 今日は悪くない一日だった。
金髪の彼女が、急いでトイレから戻ってきた直後。
それが上がったのは、まだ完全に暗くはなりきらない時間。
何発かの、控えめな花火が空で開く。
俺達は少し拍子抜けしたものの、
文化祭の一日目の最後を彩るには十分なものだった。
「今日さ、勉強の邪魔してごめん」
彼女が、ぽつりと言った言葉を、
俺は小さな声で否定する。
「まあ、悪くはなかったけど……」
二人で文化祭の感想を言い合いながら、
しばらく校庭で後片付けをする生徒達を
何気なく眺めていると….
不意に校内放送が流れ始める。
それは、俺達が所属するクラスに対して、
教室に集合を求めるものだった。
「行くしかないか」
流石にこれを無視する訳にはいかず、
二人は空き教室を後にした。
出店の手伝いを避けた居心地の悪さも感じながら、
お揃いのクラスTシャツやバングルをつけた
クラスメイトの集まる教室へと入る。
浮かれた装いに似合わず、不安そうな顔をした生徒や、
怒ったように俯いた生徒もいる。
そんな中、担任の教師が落ち着いた声で、こう切り出した。
「クレープ屋の売り上げが、一部見つからないんだ」
途端、小さなざわめきがクラスを包む。
教師は生徒達に落ち着くよう促し、
そして事の次第を話し始めた。
俺達のクラスは屋外で、クレープ屋を出店していた。
盗難防止のため、売り上げたお金を特定の時間に
教室の金庫に保管する決まりになっている。
その店から教室に移されるタイミングで、
売り上げの一部がなくなったらしい……
『盗まれた』という言葉を教師は使わなかったが、
お金を持ち逃げした人物がいるということだ。
「嘘でしょ……一体誰が……」
「みんなで頑張った売り上げなのに……」
「他のクラスの奴の仕業でしょ……」
事件の概要を聞いた生徒達が動揺を大きくする中、
俺は頭に浮かんだ言葉を口に出してしまっていた。
「犯人は、このクラスの中にいる……」
気付くとクラス中の視線が、俺に集中していた。
高校の文化祭、一日目の終わり。
クラスの教室に集められた俺達は、担任の教師から、
出店の売り上げの一部が紛失したと告げられる。
俺はその詳細を聞き、盗難によるものだと確信した。
それも、このクラスの誰かによる犯行だと……
『犯人は、このクラスの中にいる』
思わず口をついた俺の言葉は、
クラスメイト達に猜疑心や混乱を与えたようだ。
担任が必死にどよめく教室を宥める。
そして教師は俺に、
何故か少し興奮したような声で尋ねた。
「何か根拠があるのかい?」
その問いに対して、
俺は状況を整理しながら答えていく。
まず、俺達のクラスはクレープ屋を出店していた。
そこで出た売り上げを一日のうちに二回—————
お昼頃と夕方頃の決められた時間に、
担当の生徒が教室にある金庫へ保管しに行く。
教師の話では、売り上げが集金され、
教室へ移される際に紛失したということだ。
売り上げを回収する時間や方法は、
当日朝にクラスのグループチャットで通達された。
つまり、クラスの人間しか知らないはずだ。
文化祭のどこかで、
外部の人間がその情報を耳にした可能性もあるが、
犯行を計画する時間がないだろう。
「じゃあ、俺達が盗んだって言いたいのか!?」
声を荒げたのは、
売り上げの保管係だった二人の生徒だ。
「そうは言ってない。
*むしろ、真っ先に容疑者から外れる対象だ」
緊張からか、顔を赤くしている彼らを無視して、
俺は考えを進めていく。
「そもそも、何回目の保管時に、
*売り上げが盗まれたんだ?」
「二回目だ。そうだね?」
教師が、二回目の集金時に
売り子をしていた生徒に語りかける。
生徒の証言によれば……
夕方頃の集金時刻に『うさぎの着ぐるみ』がやってきて、
そいつを保管係だと勘違いしてお金を渡したらしい。
その生徒は責任の一端を感じて浮かない顔をしつつも、
状況を思い出しながら補足を続ける。
着ぐるみを見たときは怪しく思ったが、
クラスで用意した専用の『集金カゴ』を持っていたから、
売り上げの保管係だと判断をしたという。
そして着ぐるみに売り上げを渡した後に、
本物の保管係が来て、その場は改めて混乱したらしい。
教室の金庫を確認すると一回目の売り上げ分しかなく、
手分けして失われたお金の所在を探していたが、
結局今まで見つからなかったのだった……
やっぱり、と俺は思う。
犯人はうちのクラスの集金方法に精通し過ぎている。
自分が疑われたくないという意識からか、
クラスメイト達が再びざわめきだす。
そんな中で「……が怪しいよね」という声を、
俺は聞き逃さなかった。
「あの子、手癖悪いって噂だし……」
―― あの子。
それは俺が一緒に文化祭を回った、
クラスで厄介者扱いされてる、
金髪の女生徒のことだった。
そして、その一言が囁かれた途端――
教室の皆が暗黙のうちに結託したように思えた。
素行の悪い金髪の彼女を、
犯人として仕立て上げればいいのだと。
その後、クラスの全員から、
彼女をスケープゴートにした尋問が始まった。
「僕達は団結して文化祭の準備をやってきた。
*こんな酷いことができるのは準備を手伝ってない奴だ!」
「その子、バイト先でもお金を盗んだって噂だよ。
*盗みに慣れた人が犯人に決まってる!」
「お店番の担当にもなってなかったし、
*一日かけて犯行の準備をしてたんでしょ!」
自分の保身だけを考えた、知性のない戯言。
俺はそのすべての証言に対して、
論理的な破綻を指摘し、彼女の潔白を証明していく。
皆が彼女を疑う理由が、派手な見た目や、
言動の軽さなど偏見であることは明白だ。
そして、不毛な論争に嫌気がさした俺は、
彼女の完全な『アリバイ」を彼らに突き付けた。
保管係の証言によると、犯行時刻は17時ちょっと前。
俺達が花火を見に空き教室へ行ったのがその約30分後。
つまり売り上げが盗まれた時、ちょうど俺と彼女は、
一緒に文化祭の出し物を回っている最中というわけだ。
二人がグルだという反論があったとしても、
今日立ち寄った出店の生徒から証言を得られるだろう。
「彼女が犯人だと言うのなら、
*他にも条件に当てはまる奴がいると思うけど?」
俺のトドメの一言で、
クラスの誰もが何も言い返せずに黙り込んだ。
しばらく続いた沈黙を破ったのは、
事件の深刻さにそぐわない軽快な拍手。
それと共に、担任の教師が俺を称賛し始めた。
「すごいすごい!
*まるで推理小説の名探偵みたいだね!」
担任は、授業中にもよく推理小説を熱く語り、
生徒の間では変わり者の教師として認識されている。
そんな担任の言葉に、みんなは目を丸くする。
俺自身も何を言われているのか一瞬分からなくなった。
これまで黙って見ていた教師は、下校を促すように言う。
明日の金庫番は先生が責任をもって務めるから、
安心して文化祭二日目を楽しむようにと。
続けて、俺と疑われた金髪の彼女に向かって、
目を輝かせながらこんなことを口にした。
「君が主人公の探偵役なら、
*彼女は助手のヒロインってとこかな」
『二人で売り上げ紛失事件を解決する』
それが、教師が俺達に与えた課題となった。
期限は明日の下校時刻。
文化祭の二日目 ―― 最終日が終わるまで。
「皆も協力するように!」
推理小説好きの変わり者の教師によって、
文化祭一日目は奇妙な雰囲気で終わりを遂げた。
下校していく生徒達の反応は、
俺を胡散臭そうに見たり、睨みつけたりと様々だ。
もう、めちゃくちゃだ。
俺は静かに勉強をしたかっただけなのに……
教室に取り残された俺と金髪の同級生は、
無言のままお互い顔を見合わせた。
それにしても、こんな日は久しぶりだ。
俺の存在が、皆に認識されていると感じる一日は……
高校の文化祭、二日目 ―― 最終日。
期せずして、俺はクラスで起こった、
盗難事件の犯人探しに巻き込まれている。
一日目が終わろうとしていた時に、
屋台の売り上げが盗まれるという事件が起こったのだ。
容疑者として名があがったのは、
俺と文化祭を見て回っていた同級生の女生徒。
理由は簡単だ。
進学校では珍しく、彼女は髪を金髪に染めており、
普段の学校生活において素行が悪いから。
ただ、それだけだった。
証拠もなく犯人だと決めつけるクラスの皆に対し、
俺は次々と的外れな発言を論破していった。
担任の教師はそんな俺を見て、
推理小説に登場する探偵のようだとはやしたてる。
そして、金髪の彼女を助手として、
二日目が終わるまでに真犯人を探すよう命じたのだ。
―― という訳で、
俺と金髪の同級生は校庭を歩き回っていた。
横を見れば、彼女が飴を舐めながら、
元気のなさそうに俯いている。
無理もない。
昨日のクラスメイト達からの集中砲火は、
彼女の心を大きく傷つけたに違いないのだから。
「まずは『うさぎの着ぐるみ』の
*行動から調査してみるか……」
売り上げが盗まれた際、犯人と思しき人物が
『うさぎの着ぐるみ』を着ていたことから、
犯人をそう呼称している。
そいつは集金時間である17時少し前に現れ、
集金専用のカゴに屋台の売り上げを集めて消えた。
奴の動向を把握することが、
事件解決の糸口になることは間違いないだろう。
俺と彼女はクラスメイト達に聞き込みを始める。
普段、彼らとはほとんど話さないせいで、
正直なところ勝手が分からなかった。
中には俺達二人に対して、
明らかに警戒した目を向ける生徒もいる。
だが、俺がどう話しかけるか悩む度に、
必ず金髪の彼女が背中を押したり、
代わりに話を切り出してくれた。
見た目や言動から誤解を受けることが多いが、
彼女は面倒見がよく、人をさりげなく助けるのが上手い。
その姿を見る度に、
俺はある人の存在を思い出してしまう。
金髪の彼女はひとり親で、下に弟や妹がいるらしい。
弟や妹がいるとそうなるのだろうか……?
そんなことを考えていると、彼女は唐突に、
「あのさ、ありがとう」と俺に言った。
振り返ると、彼女はこう続ける。
昨日、クラスの皆が自分を疑った時、
俺にも同様に疑われることが怖かった、と。
でも、疑うどころか庇ってくれたことが、
とても嬉しかったとも……
「俺は正しいと思ったことを言ったまでだ」
「それが嬉しかったんだよ」
彼女はもう一度お礼を言うが、
その表情はよく見えなかった。
俺達は、他のクラスや部活動での出し物など、
徐々に聞き込みの範囲を広げていった。
なかなか手掛かりがつかめない調査が続いたが、
ようやく夕方頃に、俺達は妙な言葉を聞く。
「お金が盗まれたのって、花火の予行の前なんだ。
*その時間は店仕舞いで周りとか見てなかったな」
花火の予行……?
俺が聞き返すと、その生徒は、
文化祭の日程が書かれた冊子を見せてくれた。
冊子には、花火大会の日時が書かれている。
それによれば、打ち上げ本番は二日目の今日。
昨日の花火は、予行だったようだ。
だから、控えめな花火だったのだろうか?
それと同時に、何かが引っかかる。
昨日、綺麗な花火を見たいからと、
彼女は俺を空き教室に連れて行った……
「なんだ、花火の本番って今日だったんだね!」
無理に笑ったような金髪の同級生の声に、
俺は思い当たる真実を頭の中で否定したくなる。
―― でも、それはしてはいけないことだ。
「なあ……昨日の空き教室で、
*今日も花火を見ないか?」
俺のその誘いに、彼女は暫し俯いたが、
最終的に「うん」と返事をした。
教室へ向かう足取りはほんの少し重く、
昨日の気持ちとは天地の差があった。
空き教室に着いたのは奇しくも、
昨日と同じくらいの時刻だった。
昨日とは違い、外の歓声が却って虚しく感じる。
俺は教室の時計を見つめながら考えを整理し、
そして、居心地の悪い沈黙を破った。
「謎はすべて解けたよ……」
彼女は窓の外を向いたまま、振り向かない。
だから、俺は更に言葉を重ねる。
「お前が……犯人だったんだな……」
たっぷりと時間をかけ、やっと金髪の彼女が答えた。
「……証拠はあるの?」
彼女が何を考えているのか、俺には分からなかった。
俺はスマホを見せながら、酷く疲労したような声で続ける。
スマホに表示された時間よりも、
空き教室の時計の方が、30分も進んでいる。
「……案外、気付かないものなんだな」
彼女は恨みがましいような目で俺を見たが、
口には微笑みを浮かべていた。
この教室に行こうと誘った時点、もっと言えば、
今日俺と犯人捜しをすると決まった時点で、
彼女は覚悟していたのだろう……
俺が推理した、彼女の犯行はこうだ――
文化祭一日目の朝、アリバイ工作のために、
図書室で勉強していた俺を誘う。
その際、時間を隠すためにスマホを奪っておく。
俺と一日をかけて文化祭を巡り、
常に一緒だったというアリバイを作る。
そして、犯行の時間である17時少し前。
俺を時計の30分進んだ空き教室に誘い、
トイレに行くふりをして売り上げを盗みに行った。
最後に何食わぬ顔で俺の元に戻り、
隣で予行の花火を眺めれば、犯行の完成だ。
―― 黙って俺の推理を聞いていた金髪の彼女が、
「ちょっと待ってて」と言って教室を出ていく。
後を追ったりする必要はない。
そのまま彼女が逃げるとは、何故か思えなかった。
そして予想通り、彼女はちゃんと戻ってきた。
クラスの出店の売り上げを集金するための、
専用のカゴを持って……
カゴの中には、高校生にとって少なくない額の、
お札と小銭が入っている。
「そうだよ、あたしが盗んだの。
お金は着ぐるみと一緒に別の空き教室に隠してた」
「…………」
信じたくはなかったが、少なくとも、
俺の推理は的外れなものではなかったらしい。
昨日彼女との時間が楽しいと感じた分だけ、
俺は落胆を感じてしまっていた。
金髪の彼女は、申し訳なさそうにしながら、
俺に集金のカゴを手渡してくる。
それにしても彼女は、
集金方法がクラスのチャットで流れて来た時点で、
この計画を思い立ち、実行したというのか……
彼女は授業に出ないため、成績も悪く思われがちだ。
けれど本来の……もっと追い詰められていない彼女は、
今とは違う学校生活を送れていたのかもしれない。
そんな不思議な想像が過った。
同時に、推理を終えたものの、
納得のいかない点もあった。
クラスの屋台の売り上げなど、たかが知れている。
どう考えても、犯行がバレるリスクと割に合わない。
俺の視線に意図を悟ったのか、
彼女は苦し気に顔を歪ませる。
「だって、仕方なかったし……」
力なく呟いた彼女の横顔を、今日一発目の花火が照らす。
その頬には、一筋の涙が流れていた。
暮れ合いで薄暗くなった空き教室の中。
俺と金髪の女生徒が、窓の外を見つめている。
一番初めに上がった花火を皮切りに、
昨日よりずっと華やかな花火が夜空に咲く。
スマホの時計を見れば、文化祭の冊子に書かれた、
花火大会の開催時刻を示している。
それは教室の時計より30分ほどずれていた。
昨日のこのくらいの時間に、
彼女はクラスの屋台から売り上げを盗んだのだ。
拍子抜けするほどあっさりと、
彼女は自分が事件の犯人だと告白した。
そして、その動機を涙目ながらに語り始める。
「うち、貧乏だからさ。
*どうしてもお金が足りなくて」
日々の生活を送るだけのお金で、家計は精一杯だった。
弟のボロボロになった靴を買うのに、数百円足りない……
妹に可愛らしい筆箱すら買ってあげられない……
弟や妹が学校でどんな目で見られるのか、
普段の自分を見れば、嫌でも思い知ってしまう……
彼女自身も貧乏だからと、
それらしい恰好をしたくはなかったらしい。
手の届く範囲で、自分を同年代の少女のように着飾った。
しかしチープな飾りは、彼女の周囲からの印象を、
派手で素行が悪い不良少女のように見せることになった。
金髪の彼女は、学校に行く時間も惜しんで、
アルバイトでお金を稼ごうとしたという。
せめて、妹や弟だけでも、
同級生から貧乏だという視線で見られないように。
「なのに、バイト先のレジでお金が合わなくって、
*あたしが犯人扱いされてクビにされちゃった……」
それが、こんな結末に繋がるなんて
俺は言葉を無くした。
彼女の家庭環境について話を聞いたことはあったが、
彼女がそこまで追い込まれていたとは知らなかったのだ。
「あたし、どうすればよかったんだろうね……」
自分を削り、弟妹のために盗みまで犯した彼女。
俺はまた彼女を見て、あの人――
家族のために無理をする実の姉の姿を重ねてしまう……
彼女の痛々しい様とは裏腹に、花火が美しく空を照らす。
そして、俺は改めて彼女を真っ直ぐ見た。
「一緒に先生のところへ行こう」
正直に話して、クラスメイトにも謝ろう。
必要なら家庭の事情も話さないといけないかもしれない。
でも、それはしなくてはいけないことなんだ。
彼女は暫し迷った後、意を決したように頷いた。
二人で職員室へ向かう。
俺を探偵役に仕立て「犯人を捜せ」と言った、
推理小説好きの担任の教師のもとへ行く。
盗まれたお金を返し、事のあらましを話すと、
金髪の彼女は涙を流しながら謝った。
「しかし、そんなトリックよく思いついたな」
お金を数え、それが売り上げの記録と合っているのを
確認しながら、教師は朗らかに言った。
彼女を叱る風でもなく、
何故やったのか理由も聞こうともしない。
「でもさ、そんな上手くいくわけないだろ。
*推理小説ならまだしも、ここは現実だからね」
お金がすべて戻ってきたことを確認し終えた途端、
教師は態度を変えて淡々とそう告げた。
「いや……彼女は計画して……それに、事情が」
俺が焦って声を荒げると、
黙るようにと言いたげに、教師は人差し指を立てた。
そして――
「集金方法が決まったのは当日の朝だ。
*そんな手の込んだ計画を立てるなんて無理じゃない?」
「30分ずれた時計があるなんて都合がよすぎるし、
*一緒にいた君が別の時計を見ない保証もないよね?」
「トイレに行くふりをして犯行を行ったとして、
*そんな短時間でクラスの店まで行って戻れるかな?」
「そもそも、着ぐるみを着た誰かに、
*店番の生徒が売り上げを渡すとは限らないでしょ?」
教師が次々と指摘する、推理の穴の数々。
事実として、金髪の彼女はそうして犯行を成し遂げた。
だが、常識的に考えるのなら……
教師の言葉は理路整然としていて反論の余地がない。
言葉を一通り突き付けた教師は、
初めから用意していたかのように、話の結論を述べた。
「今回は生徒自ら名乗り出てくれたわけだし、
*先生とお前達の秘密にしておこう」
この学校はそれなりに名の知られた進学校で、
今回の事件を表沙汰にしたら外聞が悪すぎる。
だから隠蔽する……というのが大人側の方針らしい。
「な?」と微笑んだ教師の机にはもう、
女生徒が出来心でお金を隠すいたずらをした旨の、
校長への報告書が置かれていた。
俺の横では、俯いた金髪の彼女が、
消え入りそうな声で「はい」と答える。
「先生は、真実を明らかにしたくて、
*俺に調べさせたわけじゃなかったんですね……」
教師の思惑を察した俺は、声も拳も震えていた。
俺達だけの秘密になるのなら、
このまま事を大きくせずに済むし、
彼女も傷を曝さなくて済むはずだ
だけど、どれだけ頭で理解しようとしても、
胸の内から滾る何かが、納得を拒絶する。
この感情を何と言うのか、すぐには思いつかない。
たまらなくなって、俺は教師の言葉を
最後まで聞かずに職員室を後にした。
俺と金髪の彼女は、そのまま帰路に就く。
文化祭を終えた生徒達の楽しげな声が、
まだ僅かに校内に残響している。
そんな青春じみた音を気にする余裕もなく、
俺の頭はこの二日間の出来事でいっぱいだった。
金髪の彼女が、家庭の事情を悟られないように、
自身の容貌を取り繕っていたこと。
学校が進学校としての名を汚さないように、
事件を隠蔽しようと動いたこと。
この社会は、誰かの人生を狂わせるほどに、
他者からの見栄を気にしなければならない。
なんて生きにくい世界なのだろう……
思考の底へと深く沈んでいた俺に、
金髪の彼女が「ねえ」と声をかけてくる。
文化祭を巡った時のような明るい表情は見る影もなく、
打ちひしがれているようだった。
俺自身も今、全く同じ表情をしているのかもしれない。
「あたしがもっともっと頑張れば、
*皆からの見る目も変えられるよね……?」
彼女は声を絞り出すように言う。
その様子は、何か俺に期待を向けているように見える。
彼女がクラスの皆からかけられた疑いを、
俺が晴らした時のように
「変えられるさ」と、
言えたらどんなによかっただろうか……
彼女が求めている答えを察しながらも、
俺は何一つ声をかけることができなかった。
そのまま彼女は俯く。
顔に影が落ちて、それがどこか、
瞳から光が失われたようにも見えたのだった。
文化祭が終わり、暫く経った頃。
賑やかだった飾りは跡形もなく撤去され、
いつもの学校生活が戻っている。
俺は今日も、始業時間より早く登校して、
図書室で独り勉強に集中していた。
誰にも邪魔されない穏やかな日々。
あの文化祭からすぐ後のこと、
金髪の同級生は学校に来なくなった。
家庭の事情が関係しているのか、また別の理由なのか。
本人からの希望があったとかで、
理由がクラスの皆に伝えられることはなかった。
当然ながら俺も、
彼女に連絡を取ったりはしていない。
そんなこと、する資格がないのだから……
太陽が雲に隠れ、影の落ちた図書室。
俺は、外界から自身を孤立させるかのように、
ひたすら数式を書く筆記音を響かせ続けていた。
ママ 「佑月ちゃんって、一見クールで取っつきにくいけれど、
「 本当はすっごく優しい子なのよね」
ママ 「この間、私が『檻」で迷子になっちゃったとき、
「 心配しながら捜してくれたのは嬉しかったわ~」
赤さん 「それに、奴は案外寂しがり屋なんだよな。
「 迷子のママを見つけたときの、ほっとした顔と言ったら」
ママ 「うふふ! 口では文句を言ってたけどね。
「 『迷子になる案内人がどこにいる』とかって」
赤さん 「今の声マネ、最高だよママ。本物を越えてるね」
佑月 「おい・・・・・・二人で何話してるんだ?」
ママ 「佑月ちゃんの好きなところを、二人で語り合ってたのよ」
佑月 「またくだらないことを・・・・・・」
ママ 「そうだわ! 次は私達の好きなところを、
「 佑月ちゃんに答えてもらいましょうよ! いいでしょ?」
佑月 「急に何だ。まあ、あれだ・・・・・・ひゅ・・・・・・ふ~・・・・・・」
ママ 「えーっと、もしかして今、口笛でごまかそうと・・・・・・?」
赤さん 「ははは! 小僧、まさか口笛を吹けないのか!」
佑月 「いや、今のはちょっとミスっただけで・・・・・・」
深夜の間に沈んだ自室。秒針の進む音だけが響いている。
少年はバイトと勉強で疲れた体を、ベッドに投げ出した。
仰向けになって部屋の天井を見つめ・・・・・・彼は空想を始める。
夜空のように真っ暗な天井に――明るい星々が輝きだす。
その星々を結べば、本の形をした星座・・・・・・カメラ座、スミレ座。
天井に描いた空想の星空に、少年は星座を創造していく。
眠る前の頭の中を、できるだけ楽しい記憶で満たそうと。
――あいつ今日も独りだよ。
不意にそんな雑音が脳裏に蘇る。今日、学校で聞いた陰口だ。
少年の心臓が波打つと同時。天井で輝く星座が一つ、消失した。
バイトの先輩の罵倒、街で絡んできた大学生の馬鹿笑い・・・・・・
そんな雑音を思い出す度に、虚構の星座が次々と消えていく。
残ったのは真っ暗な天井。少年は耳を塞いで、必死に目を瞑る。
現実で唯一の救いとも思える、眠りの中へと逃げ込むために。
まだ幼い少年が、母親と姉の三人で博物館に行ったある日。
太陽系の惑星の模型が宙に吊された展示室に、
何匹もの恐竜の化石が鎮座する展示室と、少年は興味津々。
彼は図鑑で得た知識を披露したくて、展示に対する解説を始めた。
母が笑顔でうんうんと頷くのが嬉しくて、つい熱くなってしまう。
「すみません、もう少しお静かに・・・・・・」
突然聞こえた声の主は、博物館の案内員の女性。
少年は注意を受けてしまったことが妙に恥ずかしくて、
それ以降はただ黙々と展示物を見て回ることにする。
つかの間の喜びが嘘のように、暗い気持ちが心を満たしていた。
夕方になり、売店を巡ってそろそろ帰宅する時間・・・・・・
落ち込んだ少年に、姉が「冥王星」のキーホルダーを手渡す。
ただ名前がかっこいいからという理由で、少年が好きな星。
「また来ようね」と言う姉の笑顔は、太陽系の果てまで届く
光のように、少年の心を照らしてくれたのだった。
少年が中学生の頃、家族は徐々にバラバラになり始めていた。
母が借金を背負い、返済のストレスで言動が荒くなった父。
家族が崩壊の一途を辿る中、少年の姉だけは諦めずに笑っていた。
「姉さんなら、きっと家族を元通りにしてくれる」
そんな尊敬に似た感情を盾に、少年は辛い日々から逃げ続けた・・・・・・
ある日。帰宅部の少年が家に帰ると、洗面所から声がする。
皆は仕事や部活のはずだと、ドアの隙間から覗き見ると ――
そこには、姉が声を押し殺しながら泣く姿があった。
姉の手には、幾本の髪の毛が絡んだクシが握られていて、
洗面台の上にも少なくない量の髪の毛が抜け落ちていた。
心臓を掴まれたような感覚、少年は息ができなくなる。
姉が一人で抱え続けた、家族の存続という重圧・・・・・・
それから目を背け続けた自身の不甲斐なさを呪いながら、
少年は自室に籠もり、数夜に亘って己を責め続けた。
もう姉だけに背負わせない。二度と姉の前で弱音を吐かないと。
少年が幼かった頃、夏休みには家族で母の実家へ泊まりに行った。
都心から離れた高級住宅街にある邸宅、その広いリビングには、
学校の音楽室に置かれるような立派な『グランドピアノ』がある。
少年の姉が「久しぶり!」と、友達に再会したように語り掛け、
ピアノの鍵盤を覆う赤いフェルト生地を取り払う。
馴れた様子で鍵盤の上を踊る、姉の白く細い指。
母も寄り添うように指を踊らせ、共に軽快な音を奏で始める。
その綺麗な音色に誘われて、母方の祖父母も集まってきた。
リビングの窓から降り注ぐ日射しが二人を輝かせ、
まるでスポットライトを浴びるライブステージのよう。
少年は考えていた。姉と母は ・・・・・・よく似ていると。
普段から、二人の笑顔と声は周囲を華やかに照らしてくれる。
比べて自分は、ステージの光によって暗く陰になった、
有象無象の観客の一人のような気がしてならない。
眩しさの輪に入れず、彼は遠目から二人を見るしかできなかった。
『檻』を彷徨う姉弟は、深海のように薄暗い空間に辿り着く。
そこで二人の前に現れたのは、数多の光の群れ。
巨大なクラゲが空を泳ぎ、その跡を漂う幼生のクラゲ達。
幻想的な光景から目を離せず、二人はただ黙って見とれている。
少年が思い返していたのは、幼い頃に行った水族館の思い出。
水槽で漂うクラゲがライトアップによってきらきらと輝き、
それを見た姉は確か、こんな例えを ――
「ねえ・・・・・・宝石みたいだね」と、隣で姉が儚げに呟く。
思い出の中で姉が言っていた言葉と、同じ響き。
どんなに離れていても、言葉を交わすことがなくても、
二人には互いに通じ合える・・・・・・姉弟の絆があるのかもしれない。
スマホを取り出した彼らは、同じ方向へと向け、
この一瞬を永遠に残すようにカメラのシャッターを切った。
そして、二人は微笑み合う。
あの時、日食が砕け散った瞬間 ――
対立する姉弟を包んだ、太陽と月が叶えた奇跡。
どうしてこうなったかは分からない。
誰が願ったのかも分からない。
でも、今は、もう少しだけ。
また姉弟で歩めるこの懐かしさに、
浸ってもいいんじゃないかと思った。
© SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
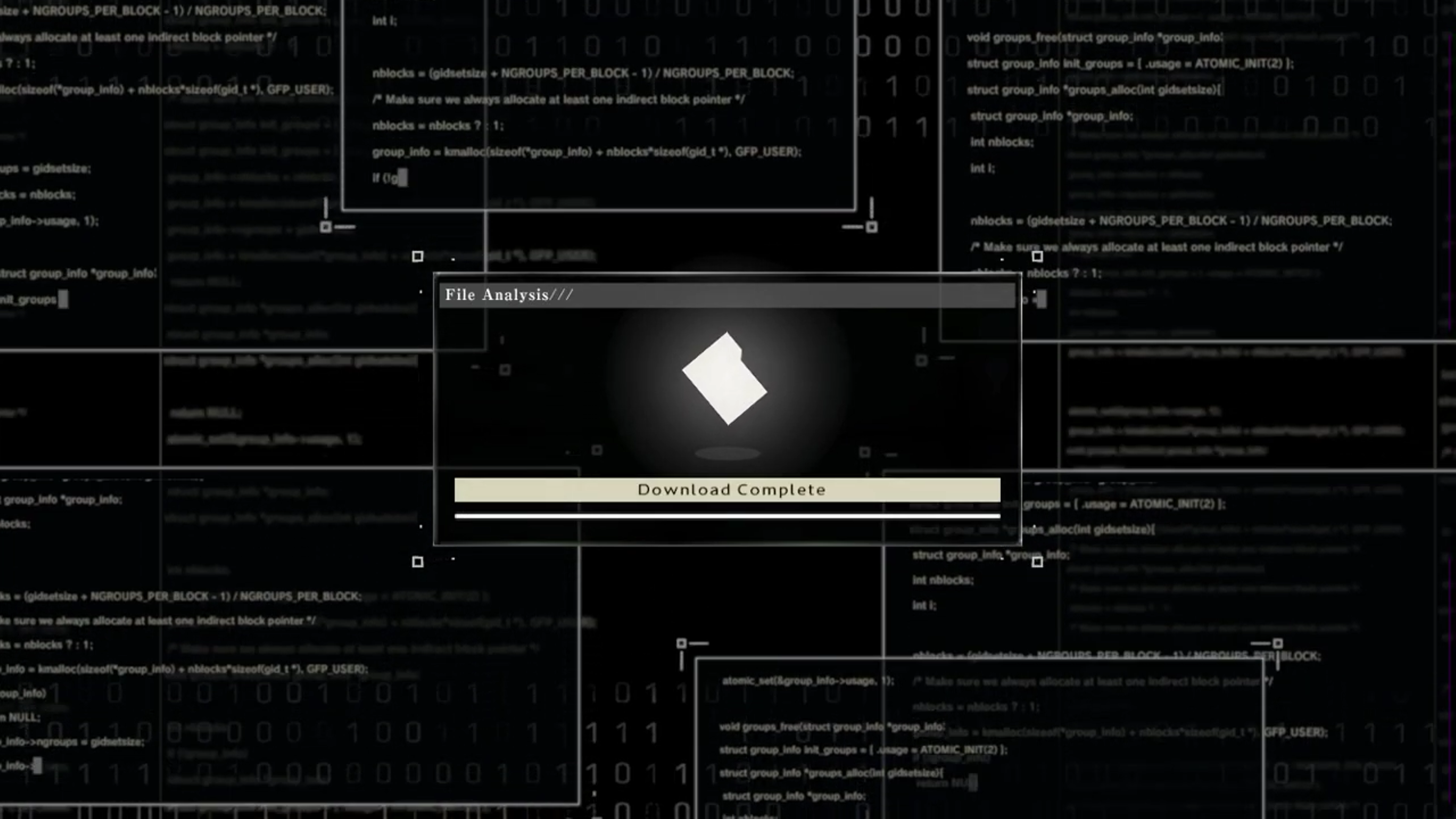








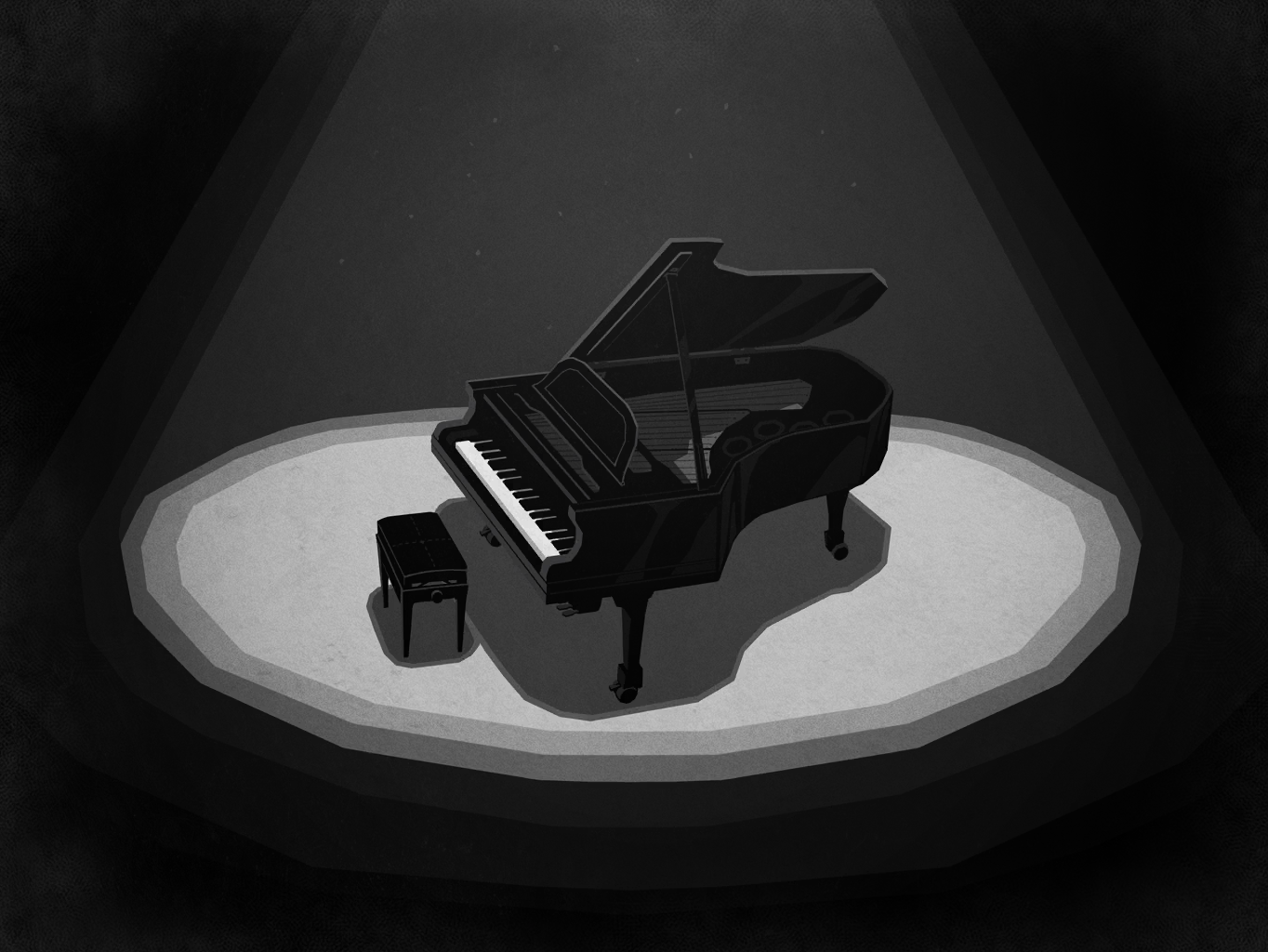



コメント