シークレットストーリー
「おかずは1日毎にパックに別けたから食べてね」
くたびれた安アパートの、四畳半の部屋の中。
冷蔵庫の扉を閉めて、私は奥の居間を振り返る。
続いて説明するのは、洗濯物や食器の扱いについて。
静かに頷く父へと事細かに話す私……
我ながら心配性だなと、呆れてしまう。
父との二人暮らしをしながらの、高校生活。
離婚前は明るく笑い優しかった父も、
今では離職して無気力になってしまっていた。
きっといつかまた、あの頃の父に戻ってくれる……
そう信じ、私は学業の傍らアルバイトをして、
家計を支えつつ家事もこなしていた。
一時期は酷い脱力状態に陥っていた父も、
病院で処方してもらった薬のお陰で最近は穏やかだ。
「それじゃ、いってきます」
――今日から修学旅行が始まる。
父の様子は落ち着いているけれど、
正直家を離れるのは、心配で気が気じゃない。
父はいつも居間の奥に座って、
映っていないテレビをぼんやり眺めている。
そんな父が、今日は玄関まで見送りに来てくれた。
「思い出……いっぱい作っておいで」
その姿に力はなく、笑顔もなかったけれど、
優しい言葉はかつての父を思い出させた。
今度の薬はよく合っているみたいだ。
必要最低限の荷物を詰めた、少しくたびれたボストンバッグ。
ほつれは目立つが愛着のあるそれを抱え、私は家を出る。
いつものクセで、扉が閉まる直前に家の中を覗くと、
父はもう私に背を向けて顔を見ることはできなかった。
スマホの時計を確認すると、
予定していた時間をとうに過ぎていた。
余裕を持って家を出るはずだったのに……
私が修学旅行でいない間の数日、
父が不自由なく過ごせるよう準備をしたのだが、
予想外に時間が掛かってしまったようだ。
慌てて走ったがもう遅く、バス停についた頃には、
車体は遠く小さくなっていた。
一瞬さっと体が冷えるが、立ち止まっている暇はない。
最寄りの駅まで走って乗り換えを上手くこなせば、
クラスの集合時間に間に合うはずだ。
ずり落ちていたバッグを引き上げ、
走らないと、と脚に力を込めた瞬間――
「すみませんね、そこのお嬢さん」
背中から急に話しかけられ、
つんのめりながら後ろを振り向く。
そこにはお婆さんが困り顔で立っていた。
「えっと……どうなさいましたか?」
乱れた髪を耳に掛けながら、
なるべく落ち着いた声で返事をする。
「ここに行きたいんだけど、迷ってしまって……」
お婆さんの見せてくれたメモには、
聞いたことのある接骨院の名前が書かれている。
「そこなら知ってますよ」
お婆さんを案内するよう歩き出してから、
はっと自分が遅刻寸前の身であることを思い出す。
けれど、幸いなことに接骨院は駅の方面にある。
お婆さんを送り届けた後、走れば電車に間に合うだろう。
足元のおぼつかないお婆さんを急かさないよう、
ゆっくりと目的地までの歩道を進んでいく。
接骨院の前まで送り届けると、
「私はここで」と微笑む。
すると、お婆さんは私を引き留めて、
数個の飴玉を手に握らせてくれる。
私はお礼を言って、改めて走り出した。
時計を確認すると、最初の想定時間より、
ちょっと遅れてしまっている。
急がないと……しかし、その時――
「泥棒! どろぼーう!!」
ただ事ではない叫び声が近くから聞こえ、
思わず足を止めてしまう。
見ると、『いかにも』という風貌の黒いマスクの男が、
コンビニから鞄を抱えて飛び出してきた。
黒づくめの男は防犯カラーボールをぶつけられたのか、
オレンジ色のペイントが背中でまだら模様を作っている。
私はひとまず驚く気持ちを落ち着かせると、
意を決して黒づくめの男の近くまで走り、
自分のバッグをその足元めがけて投げつけた。
目論見通り、男は足を引っかけて転倒。
後から走ってきたコンビニ店員に追いつかれ、
通行人の協力者達にも取り押さえられた。
店員からお礼がしたいと言われたけれど、
今はとにかく駅に向かわなければ。
私は「ごめんなさい」と頭を下げてから、
バッグを拾い上げまた走り出す。
どうして修学旅行の当日に限って、
こんなドラマみたいな出来事が起きるんだろう……
息も絶え絶えにやっと辿り着いた東京駅には、
自分と同じ制服を着た生徒達がすでに集まっていた。
私に気付くと笑顔を見せて、
こっちこっちと手招きするいつもの友人達。
皆を待たせてしまったと申し訳なさそうにしながら、
私は担任の教師の元へ向かう。
「真面目なお前が遅れるなんて、珍しいな」
教師はそれ以上私に追求することなく、
新幹線の乗り場へと生徒達を先導し始めた。
てっきり叱られると思っていたので、
私はほっと胸を撫で下ろす。
新幹線の席に座ると、ようやく一息つくことができた。
私の隣の席にいたのは、親友とも呼べる女友達。
彼女は、小学校からほとんどクラスが一緒の、
いわゆる腐れ縁の友達というやつだ。
毎日のように「一生のお願い!」と口にして、
勉強を教えてとせがまれるが、どこか憎めない。
「今日、本当に信じられないことが続いてね」
修学旅行の始まりに、いつもより声が弾んでしまう。
私がさっきまでの出来事を話そうとすると、
彼女は「ふうん」と気のない返事でスマホに目を落とした。
その素っ気ない反応に、少し違和感を覚える。
腐れ縁の友達はクラスのムードメーカーで、
さっきも、私と同じく集合時間に遅刻したことを、
面白おかしく話して皆を笑わせていたのに。
「……飴、食べる?」
私はお婆さんからもらった飴を、
ポケットから出して彼女に渡そうとする。
だけど、彼女はそっけなく「いらない」と言ったきり。
私を締め出すように、窓の外の風景を眺めるのだった。
出発前からアクシデント続きだった、修学旅行の初日。
一時は新幹線に乗り遅れそうになったけれど、
どうにか間に合って旅の目的地に着くことができた。
高くまで吹き抜けた駅の中央広場は、
美しい鉄骨とガラスの屋根に覆われている。
長らく旅行へ行くような余裕がなかった私は、
『京都』へ来たというだけで胸が高鳴ってしまう。
各々が荷物を運び、先生の話を聞いた後は、
皆お待ちかねの自由時間だ。
私の班には、腐れ縁で親友の女友達がいた。
理由は分からないが、今日の彼女は普段と様子が違う。
皆の前ではいつも通り笑顔を見せているのに、
私に対してはどこかそっけないのだ。
彼女に何かしてしまったのだろうか……
心の中に引っ掛かりを感じながら、
私達のグループは街を見て回ることに。
歴史を持つ古都の街並みはとても綺麗で、
和紙や木でできた華やかで可愛らしい飾りが、
お店の軒先にずらっと並んでいる。
他にも和菓子屋さんや、沢山の箸が並ぶお店もあり、
それぞれの風情を感じながら私達は観光を楽しんだ。
女子高生らしく友達と騒ぎながらも、頭の片隅では、
家で一人待つ父のことを考える自分がいる―
「ねえ、楽しみじゃない?」
そんな私を現実に引き戻すように、
班の友達が私の腕を引き寄せて言った。
「あ……ごめん。何の話だっけ?」
今から行く所が、班の皆が一番楽しみにしていた観光地。
友達のわくわくした様子に、私は思い出して頷く。
事前に決めた班の自由行動の日程では、
次に訪れるのは『縁結び』で有名な神社のはずだ。
はしゃぎながら向かおうとする皆に対して、
私が上の空な顔をしていると……
「そんな澄ました顔しときながら、
*狙ってる男子がいたりするんじゃないの」
と、腐れ縁の彼女が笑いながら言った。
周りは気付かなかったみたいだけど、私には分かる。
その声には明らかに、挑発的な色が含まれていた。
そんなことないよと否定しても、
なぜかくすくす笑って取り合ってもくれない。
「好きな人いるの? 誰? 誰?」と、
班の皆からも詰め寄られたけれど、
私は「いないってば」と笑顔でその場をしのいだ。
「とにかく行こうよ。
*恋の運試しもできるらしいし!」
そう言って楽しげに歩く皆の背中を見て、
私はまた少し気分が重たくなる。
日々を過ごすことで精一杯で、
恋愛のことなんて考える余裕も無かった……
私は彼女達と同じ普通の高校生だと振舞うために、
友達の輪の中に駆けて入った。
辿り着いた縁結びの神社。
その境内にある石畳の道には、
しめ縄の結ばれた二つの石が置かれている。
一つ目の石から目をつむって歩き、
二つ目の石まで渡ることができたら、恋愛が実るらしい。
さっそく友人達が順番に挑戦するが、
皆が見事に失敗していく。
二つの石の間は100メートルくらいあり、
周囲から声をかけられると方向感覚を失って、
明後日の方向に歩いてしまうようだ。
私以外の全員が挑戦したけれど、一人として成功しない。
どうやらはたから見ているより、ずっと難しいらしい。
次は私の番だと、友達から背中を押される。
「私はいいかな……」と断ろうと思ったが、
その場をしらけた空気にするわけにはいかない。
観念した私が一つ目の石に手を置くと、
ここぞとばかりに友人達が盛り立てた。
私は目をつむる。
そして、なるべく真っ直ぐ。
両手を前に突き出して、一歩を踏み出す。
時々横から導くような友達の声が耳に入ってくるが、
転ばないよう集中していたせいか、よく聞き取れない。
――やがて、手が冷たい岩肌に触れた時。
友人達の興奮したような称賛の声に、目を開く。
どうやら私は班で唯一、一回で石渡りに成功したらしい。
皆と一緒に喜んでいると、その様子を見ていたのか
別の班 ―― 男子のグループが近付いてくる。
「面白そうじゃん。俺もやってみよっかな」
それは、クラスでも成績が優秀で目立つ男子だった。
成り行きで、私達の班も彼の挑戦を見学することになる。
普段から何事もクールにこなしてしまう彼。
少し危なっかしくも私と同じく一度目で成功し、
周りの男友達に肘でつつかれながら笑っている。
彼はひとしきり称賛を受けた後、
私の元に近付いてこう言う。
「一回目で成功したのって俺らだけだよね。
*もしかして、俺らって相性いいのかもな?」
冗談めかしたその言葉の真意を掴めないまま、
私はいつものように「さすがだね」と微笑み返した。
縁結びの神社での男子との一件は、
その後の班行動の間に何度も話題に上がった。
そして何やら、この修学旅行の期間中に、
先ほどの男子が私に告白するつもりだ
という噂も流れていたらしい。
「え……?」
初めて聞く噂に、私は動揺する。
確かに彼からはよくチャットが来ていたし、
休み時間に喋ることもあったけれど、
好意を抱かれているとは思いもよらなかった。
「あんたって、昔っからそうだよね」と、
腐れ縁の友達が、少し意地悪な声で話しかけてくる。
「自分がモテるの、自覚ないわけ?」
いつもなら、この手の話題で困っている私に、
助け舟を出してくれるのに。
本当に今日の彼女はどうしてしまったんだろう……
「そんなつもり……ないよ……」
愛想笑いをして話題が次に移るのを待ちながら、
私は誰にも気付かれないように、小さなため息をついた。
お父さんを一人家に置いてきてまで参加した、修学旅行。
思い出をいっぱい作っておいでと、
父は送り出してくれたのに……
私の気持ちは暗くどんよりしていた。
腐れ縁の女友達との間には、
ずっとぎくしゃくとした空気が流れている。
その上、とある男子が私に告白するつもりだなんて、
おかしな噂までクラス内で立っているのだ。
私はできるだけその話題に触れないよう、
いつも通りの調子で振る舞っていた。
宿泊する旅館での夕食が済んで、
いくつかの班ごとに分けられての入浴時間。
旅行の日程はもう終盤に差し掛かっていて、
明日には帰路につくことになっている。
しおりを見てスケジュールを再確認していると、
私は自分のスマホが振動していることに気付く。
どうやらメッセージが届いたらしい。
『今って旅館の屋上まで来れる?』
表示されているのはクラスの男子の名前。
暑くもないのに、嫌な汗がじわりと滲む。
私は俯き、スマホの画面を眺めた。
通知に気付かなかった振りもできる……
でも――
『今から行くね』
私はそう返すと、浴衣の上に上着を着て、
屋上へと続くエレベーターに乗るのだった。
私達の泊った旅館は街の外れにあり、
その屋上から京都の街並みを一望できた。
古都の夜景はどことなく上品で、
ぎらぎらとライトで照らされた東京と違う趣がある。
「夜景、綺麗……だね」
既に屋上で待っていた男子に、声をかける。
扉を開けた音で、私が来たことには気付くはずだけど、
彼は背を向けたままだった。
隣に立つのも気が引けてしまう。
風にあおられる彼の浴衣の袖を見ながら、
私は立ち止まって彼の反応を待った。
「……来てくれてありがとな」
「うん………」
男子の声は、僅かに震えているようにも聞こえる。
しばらく沈黙が続き、私が所在なく夜景を眺めていると、
彼が「あのさ」と再び口を開く。
「俺さ……ずっとお前のことが好きだった……」
「うん……」
彼は意を決したように、振り返る。
緊張しているのか、その視線は私の目と合わない。
私は彼の次の言葉を促すために、微かに頷く。
「だから……だから、俺と付き合ってくださいっ!」
「…………」
おそるおそる、という風にこちらを見据えた男子。
私の顔は、とても困った表情になっていたと思う。
彼のことは嫌いじゃないし、
いいクラスメイトだと思っている。
でも……それだけだ。
「私……あなたが思ってるような人じゃないよ……」
私の言葉に、彼は不思議そうな表情を浮かべた。
「あなたには……もっと似合う子がいると思う……」
あなたは、私には勿体ないよ……そう結ぶと、
引き留める彼の声を聞こうとせずに、
足早にその場を立ち去った。
上手くやれたんだろうか……
これでよかったんだろうか……
迷いながらエレベーターホールに戻ると、
ソファに見覚えのある女子生徒の姿が見えた。
それは修学旅行の間、
ずっとぎくしゃくした関係のままでいる、
私の親友……腐れ縁の友達だった。
何故、彼女がそこにいるのか分からず目を向けると、
彼女は不愉快そうに顔をしかめて言った。
「……私が好きだって知ってたんでしょ」
私は彼女の言葉に混乱する。
「私があいつのこと好きだって、
*知ってたんでしょ? 酷いじゃん……」
ようやく、彼女の真意を察することができた。
この旅行が始まってからというもの、
彼女が妙にそっけなかった理由。
それは、あの男子のことが原因だったのだ。
彼がこの修学旅行中に、私へ告白することを知り、
どうしても感情が抑えきれなくなったのだろう。
私はそんな彼女に対して、素直な気持ちを話した。
親友が彼に対して抱く気持ちを知らなかったこと。
それから、今さっき彼からの告白を断ったこと。
すると、彼女は意外そうにこちらを見た。
「お似合いだから、絶対付き合うと思ってた……」
私が首を振ると、親友は「それに比べて……」と俯く。
彼女は、自身の容姿や頭のよさを私と比べてしまって、
彼に告白すらできなかったと苦しげに呟いた。
いつも明るくお調子者で、
ムードメーカーな彼女の意外な一面。o
それを見て、私は思わず驚いてしまった。
同時にそんな自分が恥ずかしくなる。
誰にだって人に見せていない顔がある。
彼女だけじゃない。私だって……そうだ……
元気のない彼女と一緒に、班が泊まる部屋へ帰る。
すると、扉を開けた瞬間、勢いよく何かが飛んできた。
私がとっさに避けると、
後ろにいた腐れ縁の友達の顔に当たってしまう。
落ちたそれは……『枕』だった。
「ちょっと誰!? 私に枕投げてきたのは!」
彼女はいつも通りのテンションに戻って、
騒ぎつつ枕投げをしている女子に混ざり始める。
「みんな揃ったし、ここから新ルール追加ね!
*投げる時に『相手に普段言えない事』を言うの」
「なにそれ。面白そうじゃん」
腐れ縁の友達はさっそく枕を掴んで、
騒がしい戦場へと参加していった。
私は反対に部屋の隅へ移動し、
上着を脱いでハンガーにかけようとしていると……
「あんたって、こういう時ノリ悪すぎ!!」
かなり強い勢いで背中に枕が当たり、私は思わずせき込む。
振りむけば、腐れ縁の彼女が複雑な表情で私を睨んでいた。
私が困ったように枕を拾うと、
「それは言えてるかも?」「言い返しちゃえ!」と、
他の子達までが私の参加を促す。
私はしぶしぶという体で「宿題忘れすぎ」と、
無難な欠点を指摘しながら彼女に枕を投げ返す。
すると先ほどよりはるかに激しい強さで、
再びそれを顔面に投げ返される。
「自分のこと、特別な優等生って思ってるのバレバレ!!」
「……なにそれ。どういう意味?」
他の女子はそれぞれ枕を投げ合っていて、
もうこちらのことを気にしてない。
だけど、私には彼女が本気で言っているのが分かったし、
その悪意のある言葉に、我慢していた感情が熱を帯びる。
「人のこと頼りすぎ! 少しは自分で努力してみたら!?」
それは、私が常々彼女に対して思っていた本音だった。
主に宿題やテスト前の勉強とか、
彼女は当然のように私を頼って楽をしようとする。
私は枕を投げた後に、
自分がそんなことを言った事実に驚いていた。
そして……私と腐れ縁の友達との、
枕と本音のぶつけ合いが始まるのだった。
「私のことお調子者のバカだと思って、
見下してるくせに!!」
「そんな被害妄想……
*努力してないからそう思うんでしょ!」
「皆に都合よく利用されてるだけなのに!!*
自分が人気者だと思ってるのイタすぎ!!」
「そんなこと思ってない!
*他人の力がないと宿題もできない人に、
*とやかく言われたくない!」
「その何でもできますって態度、ムカつく!!*
何で男子はあんたみたいなのが好きなの!?」
「それ、思い込みだから!
*勝手に勘違いして暴走して、正直迷惑!」
「勘違いしてるのはあんたでしょ!?*
なんでも持ってるくせに!!」
「私は……っ!」
「他の人より何も持ってない……!
*努力してやっとここに立ってるのに!
*友達ならそのくらい分かってよ……!!」
いつの間にか本音をぶつけ合っていた私達。
その様子に圧倒された他の友人達が、
枕を投げる手を止めて私達を見ていた。
「あの二人……ちょっとマジすぎない?」
そんな、引いたような声を無視して、
私はまた思いつく限りの本音を叫んで、
腐れ縁の彼女に思いっきり枕を投げつける。
枕投げを装った二人の大喧嘩は、
部屋に先生がきて叱責を受けるまで続いたのだった。
修学旅行が終わり、その帰りの新幹線。
隣には行きと同じく、腐れ縁の女友達が座っていた。
親友である彼女とは昨晚、
枕と本音をぶつけ合う喧嘩をしたばかりだ。
それもこれも、親友の思い人である男子が、
私に告白をしたせい……と彼の責任にしたくなるけれど、
それは単なるきっかけに過ぎない。
結局ところ、お互いにずっと、
胸にためていたものがあったのだろう。
不満をぶつけてスッキリはしたけれど、
それも一時的なものなのかもしれない。
新幹線の窓から京都の街並みが見えなくなっても、
未だに沈黙が続いている。
気まずい……
話しかけるきっかけを作れないでいると、
「飴、食べる?」と彼女が手を差し出してきた。
それは旅先のお土産屋さんで彼女が購入した、
手鞠のような形をしたかわいらしい飴だった。
「……うん。ありがとう」
私が素直に笑顔で受け取ると、
彼女はほっとした顔でこちらを見る。
どうやら、私と同じ気持ちでいたらしい。
昨日の枕投げ大会でぶつけ合った言葉は本音だったが、
それでも長い時間を共に過ごした親友に変わりはない。
からん、と口の中で転がる飴の感触を楽しむ私に、
彼女がふいに話しかけてくる。
「……覚えてる? 私が初めて失恋した時のこと」
その時のことは、今でもはっきり覚えている。
「小四だっけ? 公園でずっと愚痴を聞いたっけ」
「うん……あの時、私に付き合ってくれてありがとう」
―― 懐かしい。
彼女とは小学校からクラスもほとんど一緒で、
どの学年の思い出にも、その表情豊かな笑顔が刻まれている。
「あのね……私、最近寂しかったの」
彼女の言葉に、私は目を丸くする。
続けて、彼女は心に秘めていた想いを話してくれた。
高校に入ってからの私が、
どこか遠くにいるように感じてしまっていたこと。
公園で愚痴を聞いてくれたあの頃と違って、
無理して笑っているように思えて心配だったこと。
明るくてお調子者の彼女が見せた、寂しげな横顔。
彼女の手に自分の手を重ねながら、私は反省する。
「……気付かなくてごめん。
*私、家のこととかで頭がいっぱいで
「それだよ! そういうことも話してくれたら、
*ちょっとは力になれるかもしれないのに」
―― 話せるわけがない。
でも、彼女の言葉は心から嬉しい。
こんなに大切な友達に恵まれて、
そして寂しい思いをさせていたんだ……
それから私達は、気まずいままに終わってしまった、
修学旅行の時間を取り戻すかのように、
旅行での出来事や昔の思い出を話し、笑い合った。
そしていつの間にか、
話し疲れて眠ってしまっていた――
東京駅に着いて皆と別れた後、
ふと送られてきた班のグループチャット。
添付されていたのは、腐れ縁の友達と私が、
お互いの肩に頭を預け合って眠る写真だった。
暖かな夕焼けの日差しに照らされた二人。
口の端によだれを垂らす彼女の寝姿は、
小学生の頃の表情を彷彿とさせ、私はつい笑ってしまう。
「仲直りできて……よかったな」
―― 皆みたいにお土産は買えなかったけれど、
父に話したい思い出がたくさんできた。
何から話そうかと胸を弾ませながら、
私は自宅のアパートへと帰宅する。
そこは……
カーテンの隙間から月明かりが入る、
薄暗い四畳半の部屋。
父はもう寝ているのだろうか。
数歩部屋に入ると、少し据えたような甘い匂いがする。
畳の上に、酒瓶が転がっているのに気が付く。
「お父……さん?」
父は布団にもぐりこんだまま、こちらを見ようともしない。
ちゃぶ台の上には、全く手つかずの状態の薬。
そして、部屋のあちこちが苦しんだ父の痕跡で荒らされ、
私が留守にした数日間を想像させた。
こんな状態のお父さんを放って、私は……
果てしない罪悪感が、胸の内を満たす。
友達と一緒に新幹線に乗って、観光地を巡って。
夜景の見える場所で、クラスの男子に告白されて。
そして、親友と大喧嘩して、仲直りして……
まるで青春のすべてが詰まったような、数日間。
そんなきらきらした思い出達が、幻のようにぼやけていく。
なのにどこか安心するような、あるべき場所に帰ったような、
そんな気持ちになることを不思議に思った。
不意に、スマホがメッセージの受信を告げる。
見ると、友人達との思い出話のやり取りを押しのけるように、
アルバイト先からのメッセージが届いていた。
―― 他人に話すことなど、絶対にできない内容。
スマホの画面を見ながらしばらく硬直していると、
さらに新しいメッセージが届く。
腐れ縁で親友の彼女からだった。
『これからは何でも私に話してね。
*頼りないかもだけど、私はずっと味方だからさ』
いつになく真面目な言葉に照れたのか、
その後にふざけた顔文字が連なっていた。
彼女らしい……と、私は思う。
でも、ごめん……私は……
何分もかけて文面を考え、
『何かあったら真っ先に相談するね!』
と彼女に返すと、今度はバイト先へ返事を打ち込む。
『数日間、お休みをありがとうございました。
*また明日から頑張ります』
だって、お父さんのためだもの。
月が雲に隠れ、闇に飲まれた部屋の中。
スマホの画面を消して、
私は眠っている父の横に座った。
お父さん……私、いっぱい思い出作ってきたよ。
私にとって、最初で最後の高校生らしい思い出。
そんなもの、できないまま卒業すると思っていた。
だから、もう十分。これで十分。
「……ただいま」
微笑みと共に囁やかれた小さな叫びは、
どこまでも渇ききっていた。
パパ 「旅の中で観た『過去』の記憶では、
「 陽那ちゃんはまさに完璧な優等生って感じだった」
パパ 「だけど、僕と一緒に歩く『檻』での彼女は、
「 どこか雰囲気が違うように思えるんだ」
パパ 「この前、僕が黒い鳥に突かれてるのを助けてくれて、
「 そういう優しいところは変わらないんだけど」
パパ 「高くて足場の狭いところとか、雷とかを怖がったり、
「 たまに心細そうに遠くの景色を見つめたり……
「 どこにでもいる普通の女の子って印象を受けてね」
パパ 「もしかしたら、『檻』で見せる表情のほうが、
「 陽那ちゃんの本当の……」
陽那 「独り言をしながらスマホを持って、何してるんですか?」
パパ 「やあやあ、実は僕も日記をつけようと思ってね。
「 陽那ちゃんも旅のことをスマホに記録してたでしょ」
陽那 「そうなんですね……って、あれ?
「 どうして私の日記のこと知ってるんですか……?」
パパ 「ちょっとこっそり覗いて……あれあれ、陽那ちゃん?
「 そんな軽蔑したような目で見ないでくれるかな……?」
高校に通う少女の日常。授業の合間の休み時間――
教卓に積まれたプリントの山を前にして女教師が困っていると、
すかさず少女は手伝いを申し出て、職員室へと運んでいく。
少女が教室へ戻ると、今度は勉強を教えてほしい友達に囲まれる。
彼女は嫌な顔一つ見せることなく、皆に優しい声音で応えた。
学校が終わり、自宅への帰路―――
少女はスーパーへ駆け込み、家計のために特売の食材を買い込む。
一緒に暮らす父の健康も考えながら、献立を決めないといけない。
晩ご飯を済ませ、居間で父親が就寝した後――
少女は節水を心がけながら静かに食器を洗い、シャワーを浴びる。
そして、父の眠りを邪魔しないようひっそりと台所の電気を点け、
教科書とノートを床に広げて宿題と予習に取り組み始めた。
夜が深まった頃―― 少女はようやく布団に入る。
誰にも干渉されない、気遣い地獄から解放される唯一の時間。
彼女はそれを安らぎと感じる間もなく、気絶するように眠った。
小学生の少女が、父親と弟の三人で遊園地に行ったある日。
人気アトラクションの列に並んでいる最中、
父親は日射しに当てられ、ふらふらになってしまっていた。
「お父さん大丈夫?」と少女は甲斐甲斐しく世話をして、
売店で冷えたお茶のペットボトルを買ってくる。
そして、父親へ渡そうと蓋を開けたその時――
弟に袖を引っ張られ、お茶は地面に落ちて零れてしまった。
少女は本気で父親のことを心配するあまり、
弟に「ちょっと、あっち行ってて」と冷たく当たってしまうのだ。
うつむく彼を見て、少女は後悔しつつも父の手当てに戻る。
思えば、休日のお出かけが嬉しくて、父親とばかり話していた。
構ってもらえない弟が、拗ねてしまってもおかしくはない……
父親の体調が回復した後、少女は弟に謝ろうとするが――
人混みに紛れて消えたかのように弟の姿はなく、
彼が被っていた帽子だけが、寂しげにその場に落ちていた。
少女が中学生の頃、家族は徐々にバラバラになり始めていた。
母の借金のせいで、返済に苦悩し変わってしまった父。
家族の仲を取り持とうと、少女はできる限りの努力を続けたが、
どんなに手を尽くしても家の空気は沈んだまま……
一人で喋ったり笑うことが滑稽で、彼女は自信を失ってしまう。
少女はある日、ずっと皆勤賞だった学校をズル休みした。
ベッドに寝転び、天井を眺めて過ごす虚無のような一日。
夕暮れ時にスマホの通知音が鳴り、それを手に取ると――
画面に映ったのは、ヒヨコのぬいぐるみの写真に添えられた、
「いい感じのヒヨコいた」という弟からの短文のメッセージ。
抱えていた重荷が少しとけたように、唇が綻ぶ。
昔から弟はすごかった。どんな状況でも動じることがない。
崩壊する家庭の中で、一つだけでも変わらないものがある……
それがどれだけ心強くて、勇気をもらえることなのか。
弟の前では絶対に弱音をはかないことを、少女は決意した。
少女が幼かった頃、夏休みには家族でキャンプへ出かけていた。
皆でテントを張って、バーベキューコンロでお肉を焼いて……
そして夜が更けると、キャンプ場は空一面の星々に囲まれる。
父が自前の『天体望遠鏡』を設置すると、
興味を抑えられない様子の少女の弟が、一番始めに覗く。
「ほら、あの二つ星のほうを見てみようか」
父が望遠鏡の扱い方を教え、弟が星について知識を披露する。
共通の趣味を持つ親子の、微笑ましい光景……
それなのに何故か、少女は心の内で喪失感を覚えてしまうのだ。
天体観測もカメラも、弟の趣味はお父さん譲りのものばかり。
私のほうが先に産まれたのに。私のほうがお父さんを好きなのに。
どうして私は、弟がいる場所にいれないんだろう……
夜空で明るく輝く二つ星。少女はその周辺に散る星のように、
ぽつんと立ち尽くして、決して近付けない二人を眺めていた。
『檻』を彷徨う姉弟は、ビル群が立ち並ぶ空間に辿り着く。
そこにあったのは、両親の離婚前に家族で暮らしたマンション。
自分達が過ごした家が、何故ここにあるのだろう……
ビル内へ続く通路を見つけ、マンションの部屋まで入ると、
そこは壁紙の傷や置かれた小物まで、当時の思い出のままだった。
少女と弟は懐かしさを感じながら、互いに家を調べ始める。
キッチンには、幼い頃に使っていた子供用の包丁。
休日になると弟と一緒に、よくオムライスを作ったっけ……
少女の私室には、ベッドの枕元に置かれたヒヨコのぬいぐるみ。
嫌なことがあった日に、抱きしめて寝たりしたな……
最後に、二人はリビングへと集まり、写真立てを手に取った。
家族みんなが笑顔で写っている家族写真……
もう帰れない思い出に、姉弟はただ黙って想いを馳せた。
それと同時に、二人は違和感を覚える。
あの時、日食が砕け散った瞬間――
対立する姉弟を包んだ、太陽と月が叶えた願い。
二人は確かに、大きな「何か』を失った。
それは、人生をかけて背負うほど大事なことで。
でも、きっと思い出さないほうがいいことで。
胸に開いた穴の正体に気付くことなく、
脱け殻の二人は『檻』の旅へと戻っていった。
© SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
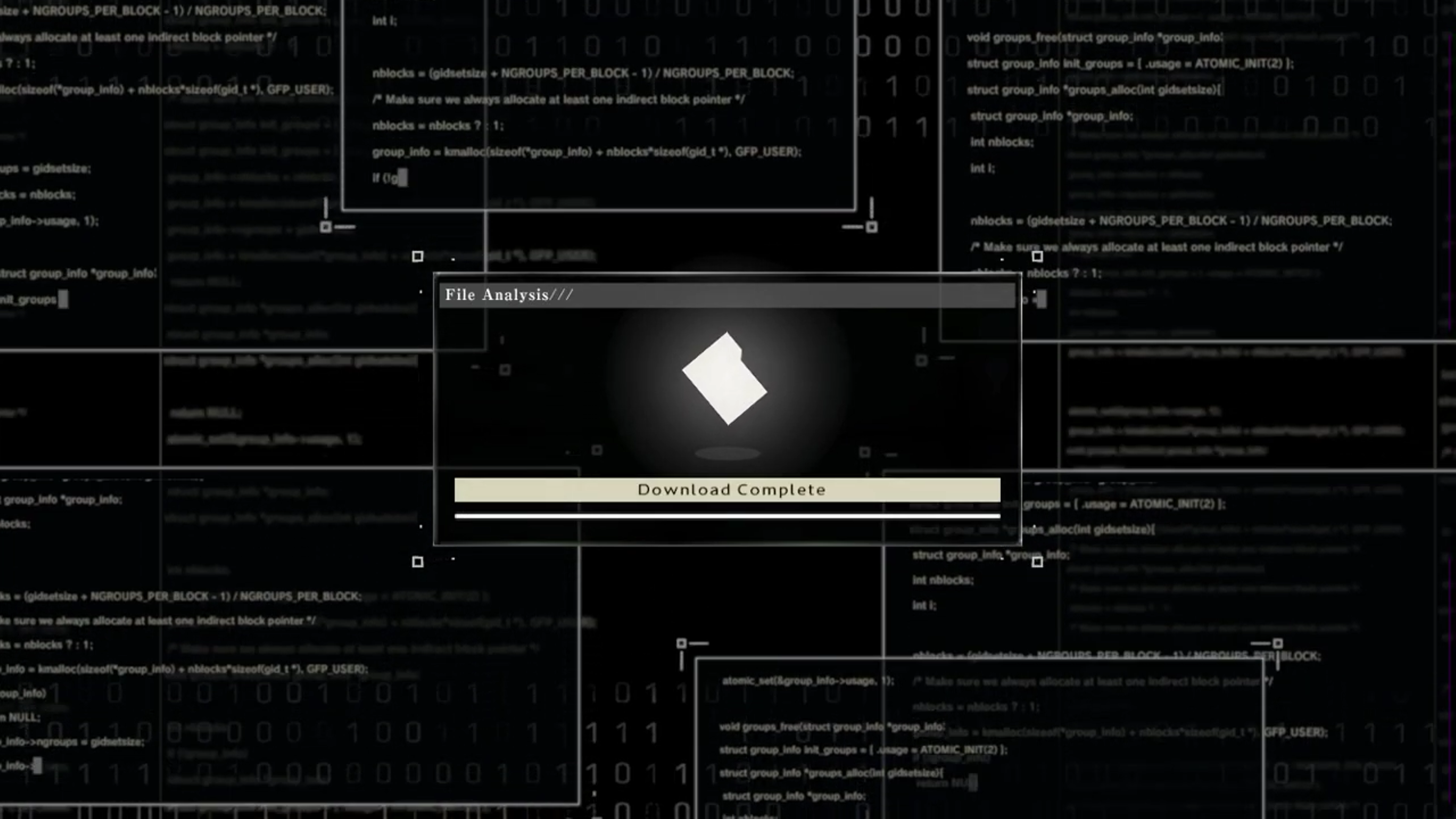





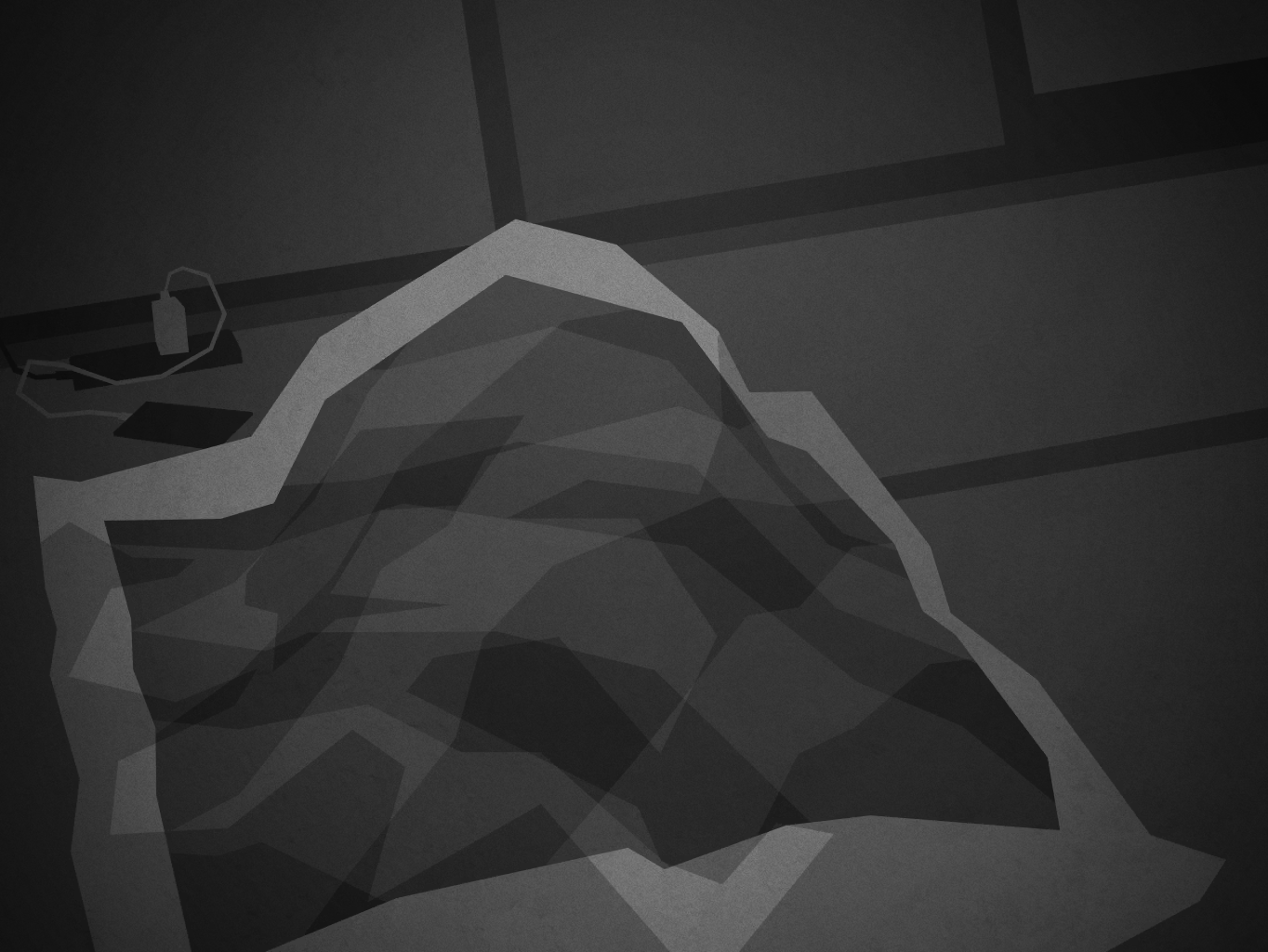






コメント