シークレットストーリー
風に流れる落葉が、庭の砂を掠め取って行く。
視線を奪われ、陽射しに目が眩んだ。
目蓋を開くと、
落葉はその儘子供達の足元の方へと流れる。
だが彼等は気にも留めない。
気付いてさえ居ないのかも知れない。
只、私は眼で追って仕舞っていた。
赤い針の目立つ塀、それに囲まれた空の下。
子供達は掛け声を上げながら、皆で何かに取り組んで居る。
未熟な四肢や筋肉故か、其の動きの統率は完全とは言えず、
元気な声は空回る様に天へ響く。
人に依っては微笑ましくも感じるのだろう。
塀の外からであれば、
子供達が手に握る物も見えないのだから。
彼等はお互いがお互いの動きを観察出来るよう、
三角形の形に向き合い、真剣を振るって居る。
立ち合いを除いては、
幼くとも真剣を握るのがこの家の流儀だ。
私達は御屋形様の刃として、あらゆる武器を、
己が手足の様に扱えなければ為らないが故に。
「……はぁ」
溜息を吐いて、一度視線を外した。
子供達から離れた位置で、
私と同じ様に彼等を見て居た人物が此方に頭を下げる。
彼が教官なのだろう、私は軽く手を振って応えた。
―― この家は、殺人鬼の組織だ。
大名の支配を影より支え、それを堅固なものとする為に、
殺しの技を何代にも亘って磨いて来た、殺人者の群れだ。
……今は私が長を務めるこの家を誰かに説くなら、
こう表すのが正しいのだろう。
この家には当主の座を代々担う血筋の人間と、
その傍系の人々が属している。
当初から此処迄の規模だった訳では無いが、
支配圏の拡大や戦力の確保、親戚間の争いや秘密の保持、
幾つかの理由を伴って、今の形態に落ち着いたと聞く。
当主には主君依り賜る直々の命が有る為、
組織としての管理を担うのは先代の当主 ―― 私の父だ。
だが、家の代表である私に無関係という事はない。
―― 今や私も、あの子供達の未来を左右する立場に在る。
子供達が取り組んでいるのは暗殺に関わる鍛練。
腰に差した打刀は当世に於いては最も一般的な武器だが、
当然、暗器に比べれば暗殺に適した武器とは言えない。
然し準備が不十分だった際や、任務中に破損した場合等、
時として得物を選んで居られない場面が有る。
あれは、その時に備えた鍛練だ。
……そうだ、私達は選べない。
幼く、無垢で在るが故に、
過酷な鍛練へも一心に励む子供達。
未だ命の重さを知らぬその瞳も、
熟れ昏い道へ踏み込んで行くのだろう。
―― 思い出すのは己の過去。
私が初めて人を殺めた日。
あの日の血に汚れた自らの手を、
康者の山私は未だ瞼の裏から振り払えずに居る。
多くの武家の子供が、漸く木刀を手にし、
父やその部下の手解きを受けながら稽古を始める年頃。
知らぬ間に朝を迎える寝苦しい夜に似た、
天地が輪郭を失って混じり合う様な暗闇の中で。
私は、緋色に濡れた自分の手を見下ろしていた。
それが、私が初めて人を殺した日。
忘れる事も、割り切る事も出来ぬ過去。
当時。
家を継ぐ立場で在った私も、あの子供達と同様、
父の部下である男の指導の下、鍛練に臨んでいた。
昼夜を問わず、連日続く過酷な修行。
時折塀の外から聴こえる、子供達の楽し気な声に、
興味の無い振りを装いながら。
―― 今になって思えば、
教官の男の苛立った様な態度も、厳しい稽古も、
彼が私を、当主の娘と云う存在を嫌ったが故なのだろう。
息を吸い込み、男の太刀筋を見極め、
私は刃の隙間に身体を滑り込ませる。
子供の膂力や腕の長さで成人に敵う筈はない。
駆け引きに持ち込むのは、体格的な不利を潰してからだ。
対等に近い状況から、判断の過ちを誘う。
そんな事を考えていたのを覚えている。
懐に潜り込まれた程度で怯む者等この家には居ない。
教官は素早く軸足を切り替え、足払いを繰り出す。
私はその勢いを殺そうと、木刀の柄を膝の皿に叩き込んだ。
相手の左側へ抜ける様にしてこの儘、胴へ刃を――
次の手に移ろうとしたその時。
視界の端に、刀身を握り、短く持ち直された木刀が映った。
踏み込んで避けるには遠く、後ろへ躱すには遅い。
私は咄嗟に男の服を掴み、体当たりをしようとして気が付いた。
助走も無く子供の体重をぶつけた所で効果は薄い。
体格的な不利を、自ら駆け引きに持ち出して仕舞った、と。
失敗を悔い、痛みに備えると教官の動きが止まる。
背後から気配がして、私は振り返った。
其処に立って居たのは当時の当主である、私の父。
父は、木刀を納めて膝を突く教官に軽く挨拶をすると、
私の眼を見て重々しく言う。
「話が有る、付いて来い」
招かれた当主の居室で話されたのは、
私にとって初の実戦となる任務についてだった。
命令が下る予兆は無かったが、
こう云った話をされた時点で続く言葉は予測出来る。
父は依然重々しく、冷たい声で淡々と語った。
娘の成長を確認したい、首を持って来い、と。
そして父は続ける。
「だが、標的は自分で選べ」
「その首の価値を以てお前の価値を断ずる」
首を垂れて話を聞いていた私は、それを聞いて顔を上げる。
予想だにしない言葉だったからだ。
猶予は五日。
父や家の利益となる者を自ら考え、選び、殺せ。
任務の指示も、父と娘の会話の内容も、
それだけだった。
返事も出来ぬまま、私は頭を下げ、
父の居室を後にする。
与えられた期間の中、どの命を奪うのが正解か。
私はその問いに囚われ、追い詰められていった。
命の価値を測る事。
それが許されるとすれば、何者だろうか。
然し、許されなくとも人は望む。
この命の価値が、そう定められていた様に。
―― 幼き日、私へと初めて下された殺しの任。
自ら定めた標的を殺める事で、自身の力量を示す試練。
私はその標的を探す為、家の者の監視下で、
市中へ出る事を許された。
諜報などの任で家の外に出た事はあれど、
それは移動に過ぎない。
自分の意思で行先を探すのも、私にとって初めての事だった。
与えられた候補から正解を探し、選択する。
実態は自由には程遠い。
だが私はこの日、自由を誤解したのだろうか。
その怖れが、私の影を家に縛り付けたのならば。
……何て、皮肉だろう。
市中を進む中、私は家を出る前に聞いた言葉を。
任を受ける前の鍛練で、
教官だった男から言われた事を思い出していた。
『力不足と思われれば、お前とて殺される』
父の満足する首を差し出さねば、私も首を取られると云う。
命を奪う事への迷いと、試練に対する重圧。
そしてその言葉が、幼い私を充分過ぎる程に追い詰めた。
震える指先を拳に隠すようにしながら、
私はどうにか標的を探し始める。
建物の隙間、狭い路地。
陽の差す通りと明暗を別たれたその場所で。
あの武士を消せたのなら、力量を充分示せる。
―― 初めて殺す私に、殺し切れるか?
舞い込んだ富に溺れているあの男は、殺し易く利益も望める。
―― だがそれで、父は満足するだろうか。
民の不興を買ったあの商人ならば、死を望む者も多い。
―― それを、私が判断して良いのか?
そうして、思考は行き止まりに辿り着く。
期日の日まで同じ事を繰り返し、
私は何時も、最後は明暗の境界をただ見詰めていた。
期日は迫り、気は逸る。
最後の日は市中の何処へ向かったのだったか。
私は毎日、必死に標的を追い求めた。
そして、無様にも毎晩迷いを連れて帰っては、
自室の壁に並ぶ武器を眺め、震えていた。
誰なら殺せるか。
誰を殺すのが適切か。
誰なら殺しても良いか。
どう殺したら、何で殺したら。
いつ殺せば、何処で殺せば――
―― 私は正解なのだろう。
そんな物が在るかも分からない。
だが私は、正しい『殺す相手』を死に物狂いで追い、
この任務と云う問いの、解となる標的を探し求めた。
―― 自身の首を賭けさせ、幼子に命の値踏みをさせる。
恐らく、この試練の目的はそれだ。
負荷に感覚が壊れるか、精神が壊れるか。
それでも家に利益をもたらせるのか。
そして、この家に生まれた者が殺しを躊躇うなら、
それは余計な事を知ったから。
無価値な憧れを砕く意味もあったのだろう。
煩悶と憔悴の中で迎えた期限の日。
私はそれが、『命』である事など忘れていた。
血に汚れた自身の掌に気付くまで、私は。
私への苛立ちを隠さなかった瞳が濁っていくのも、
その指先が弛み、緩やかに地面を撫でていくのも。
まるでそう在るのが正しいかの様に、見下ろしていた。
足元に横たわる躰。
蝋にも似た、生気の無い瞳。
鮮烈に紅が咲く。
惨憺と緋が散る。
掌が照り返す赫い光を眼に、私は漸く思い出した。
堀の内にいた己が歩む道と、塀の外の子供が行く道。
その違いに、疑問を抱いていた事を。
それを、自ら手遅れにした事を。
私はこの時、私をも殺したのだ。
父より課せられた試練への解として、私が手に掛けたのは、
任務の前に私の教官を務めていた男と、その弟であった。
元よりこの家や当主に不満を抱えていた彼等は、
家を継ぐ立場に在る私が、
任務に依って疲弊しているのを好機と捉えたのだろう。
好機と捉え、油断したのだろう。
私を利用し、当主をその座から引き摺り下ろす。
その算段について論議する彼等は、
夜陰と屋敷の陰にいた、私の存在に気付かない。
任務の期限まで僅か。
追い詰められていた私は彼等の会話を聞いて、ただ思った。
『裏切り者を消せば喜ばれる』と。
殺すという過程など、考えてもいなかった。
―― 月光の下、血飛沫が舞う。
そうして、私は二人の首を以て父に認められた。
闇討ちと言えど、顔を知る相手でも始末できる能力を評価された。
―― あの時の父の表情を思えば、
裏切りなど知った上で、私を試していたのかも知れない。
念入りに血を洗い落とした手が冷え、
まるで祈るかの様に、膝の上で両手を組み合わせていた私。
それを見て、よくやったと、父が淡泊に言葉を掛けた。
試練よりの解放を示す言葉。しかし。
私は、その日から『人斬り』としての道を歩み始めた。
幾度となく鮮血に塗れたこの掌。
何度洗っても。
洗っても、洗っても、洗っても。
自分が人を殺す鬼である事実は、二度と洗い流せない。
二度と、他の道を歩む事は叶わない。
―― 故に、私は考えていた。
視線の先で鍛練に励む、この家の子供達。
未だ外の世界を知らず、今居る世界の実情も知らぬ童に。
……私は執れ、同じ事を強いるのだろう。
あの日の父の様に、当主の座に在るのならば。
間違って居るとも思った。
然し、私が歩んで来たのは殺しの道。
全てを投げ打ち、子供達を家から解放したとしても、
その先に待つであろう問題から、彼等を護れる保証など無い。
裏切りを企てた彼等が、私に首を落とされた様に。
それに――
籠から放たれた鳥は、意思を手に入れた人形は。
何処へ旅立つのだろうか、
旅立ち方を、知っているのだろうか。
―― 私は、どうだろう。
過去や責任、或いは未来が自由を奪う。
雁字搦めの輪廻が、私の前にも繰り返されて来たのかも知れない。
選択の権利を持ちながら、答えを出せない自分。
それを呪う事しか、今の私には出来なかった。
家とは、一族の集まる場所。
族とは、人が人のために作った概念。
それは意志を持たぬ存在。
ただの言葉でしかない――はずだったわ。
けれど、いつしか家という意思を持たぬ存在こそが、
その一族の本質となってしまったようね。
一つの信念のもと、
私心を捨てた者達によって構成されるその家は
何よりも強く、何よりも恐れられたわ。
でも彼女だけは違う。
たった一人、どこか遠くを見ているわ。
屋敷を囲う高い塀の向こう。
牢獄のような家の中から、外の景色を・・・・・・
俺の店には、一人常連のお客さんがいる。
いつも一人で、茶を一杯、団子を一皿分だけ食べていく女性だ。
刀を差しているから、きっとある程度身分の高い人なのだろうが、
彼女の事も、うちの茶屋を気に入ってくれた理由も俺は知らない。
ただ・・・・・・俺は一時期あの女性が怖かった。
だってあの服の家紋は、『鬼の巣』と呼ばれている屋敷の物。
おどろおどろしい雰囲気から、誰も寄り付かないあの屋敷だ。
けれど、考えてみれば『鬼の巣』だとかは噂でしかない。
お客さんに尋ねても、彼女を知る人はいなかった。
噂で人を判断して、常連さんを探るなんて店主として恥ずかしい。
―――だから俺はその日、注文より多く団子を作ったんだ。
「すみません、これ。いつも来てくれているお礼です」
俺がそう言って二皿分の団子を渡すと、
彼女は驚いた顔をして、ありがとうと言ってくれたのだった。
「帰ったよ」
「あ、おかえりなさい」
「ん・・・・・・なんだい、この植木鉢」
「その花ね、今日お寺の方の手伝いで買ったの。
私が眺めてたら、沢山生えてるから分けてあげるって」
「・・・・・・親切な人だね。今度礼に行かないと」
「うん。それで、折角だから赤と青に近い色の花を買ったんだ」
「『折角』・・・・・・ 何か意味があるのかい?」 「だってほら、私達の名前にぴったりでしょう?」
「いや・・・・・・これ、余り緋って色じゃあないだろう・・・・・・
藍には、まぁ近いだろうけど
「いいの! ちょっとした気持ちの話なんだから」
鬼の巣とも呼ばれる屋敷の中は、異様な空気に包まれていた。
恐ろしき無敗の『犬』の手足となり、時に牙ともなる猛者たちが、
広間に集まり膝を突き合わせている。
対立する大名の跡取りを消す。其の任務は為された。
然し肝心の遺体が見つかっていない。
何より此の家の当主である女が、有ろう事か標的の屋敷で
大立ち回りを繰り広げ、数多の武士を切り伏せたのだ。
彼女は傷ついた体を引きずり、血痕だけを残し煙のように消えた。
死んでいれば其れで良い。だが、生き永らえていたとすれば。
当主であった女は、此の家のあらゆる事柄に通じている。
身の内に居るのであれば薬となるが、背を向けたならば毒となる。
「探せ。あれを生かしておいてはならぬ」
其れに応えるよう、鯉口を切る音が広間に響いた。
黄昏時、瞼を通り抜ける斜光。
視界は締に染まり、微かに鼓動が聴こえる。
その血の帳の中に、女はある景色を見ていた。
同じ色の掌を、足跡を。
全てを塗り潰す雨音の中、少女と出会った日を。
この命と引き換えに、同じ傷を抱く少女を救おうとした。
だが、女は想う。
それは少女の人生を利用し、
自らをこそ救おうとしていたのではないか、と。
―――救えた筈の命を、幾度も手折った身の上で。
女は独り己を恥じ、責める。
彼女の笑顔を見てしまえば、
血に濡れた自身の手を忘れそうになるから。
或る日、私達の家から当主が消えた。
この残酷な世での生き方を、殺し方を、私に教えてくれた人。
実の関係でなくとも姉と呼んで慕うに相応しい、
私を『鬼』にしてくれた人が。
最優の剣士を喪った空席は、私の地位を繰り上げ、
同時に、家へ混乱と角逐をもたらした。
当主の血筋でない者が御屋形様からの命を請ける事、
それを許せない、といがみ合いさえ起きている。
下らない。権威も、政治も、私は興味がない。
あの人はそれらに心囚われず、誰も及ばない力を誇ったのだから。
私は今も探している、返り血の緋を際立てる麗しき白磁の肌を。
骸を見下ろす、夜に似た深く冷たい眼差しを。
「ねえ、姉様。一体・・・・・・何方に?」
© SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
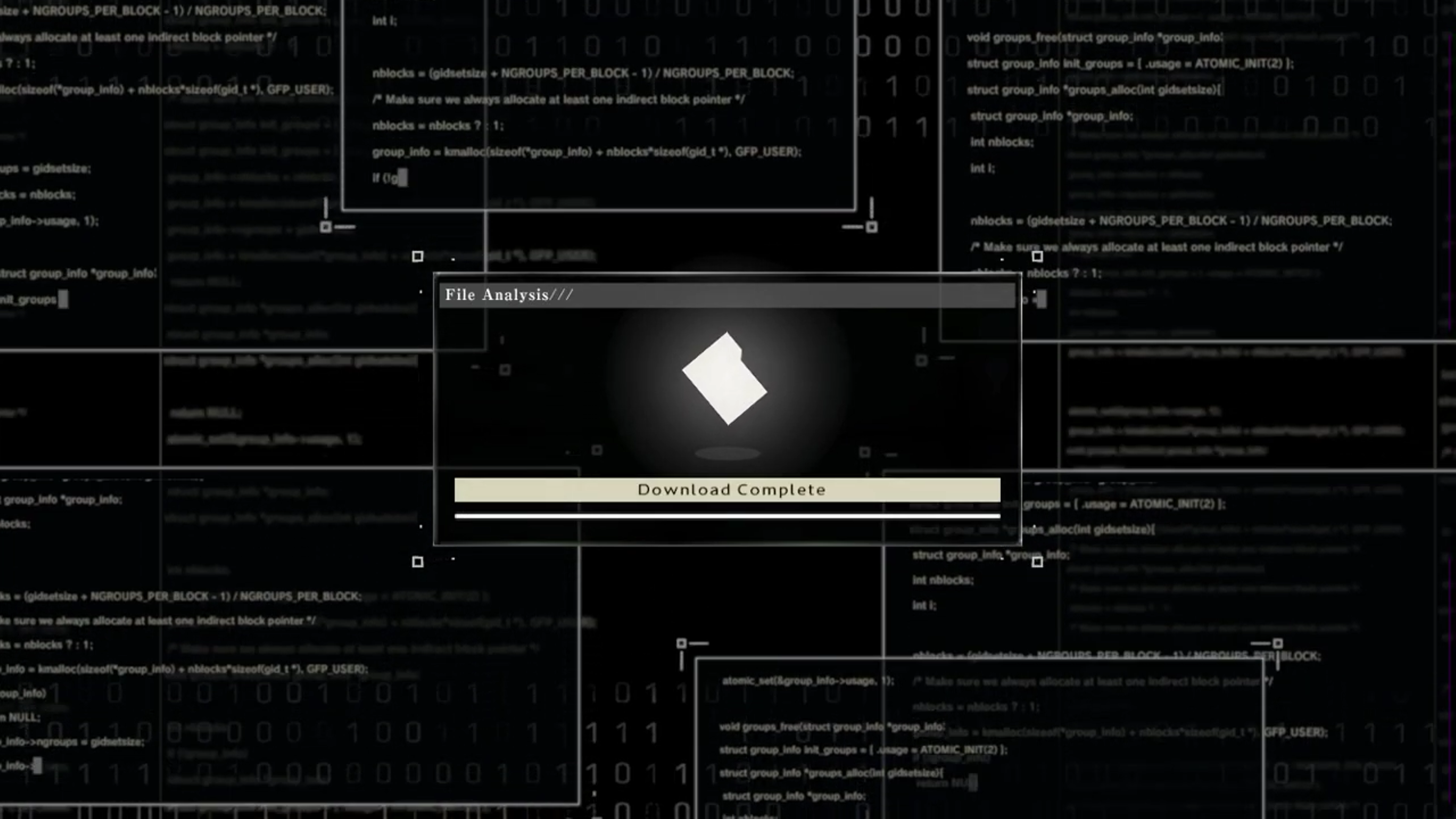












コメント