シークレットストーリー
埃っぽい、ゲームセンターの空気を吸い込む。
筐体に取り付けられたスピーカーから、
シンセサイザーの音が弾けた。
目の前のディスプレイがカラフルに明滅し、
ゲームが始まる。
音楽に合わせディスプレイに表示される、
音符のようなマーク。
その表示タイミングに合わせて足元のパネルを踏み、踊る。
それがこのゲームのルールだ。
俺はステップを踏む。夢中になって、風を切るように。
シンセサイザーの波に乗って、全身でゲームを楽しむ。
家のことも学校のことも全部忘れて、俺は踊り続けた。
やがて、音楽が終わる。オレは足を止め、ひとつ息を吐いた。
身体の中から熱気が逃げ出し、急激に現実へと引き戻されていく。
ディスプレイに表示される、ユーザー名「レヴァニア」のスコア。
悪くないスコアだが、今となっては競う相手もいない。
こんな時代遅れのゲームが残っているゲームセンターはもう、
世界に数えるほどしかないだろう。
俺は視線を隣に動かす。このリズムゲームと同じ筐体が、
もうひとつ置かれている。
本来ならふたつの筐体を使って誰かと一緒にプレイしたり
スコアを競い合ったりすることができるのだが、
今は埃をかぶった化石のように、静まり返っている。
昔ならば……隣の筐体の前には、母がいた。
俺は幼い頃のことを思い出す。
習い事の後に、よく母と一緒にこのゲームで踊った。
不器用な母はダンスも下手で、
彼女が無様なステップを踏んでは、ふたりで笑い合った。
そうしながら、父が車で迎えに来てくれるのを待っていた。
―― だけど、もう母はいない。
彼女は半年前、長年患っていた病で亡くなったのだ。
色んなことを思い出しながらぼんやりしていると、
背後から近寄ってきた店員が俺に、もう帰るように告げた。
街の条例で、未成年は夕方6時までに
ゲームセンターを出なければならないことになっている。
俺はスクールバックを手に取り、家路についた。
アパートの部屋に帰ると、父がいた。
いつもは深夜まで働いている彼が、夕方に家にいるのは珍しい。
彼は狭いキッチンで料理をしながら、「おかえり」と言った。
「帰り、早いなら連絡しろよ」
俺は苛立ちをぶつけるよう、
音を立ててスーパーの袋を机の上に置いた。
……夕飯の用意があると知っていたら、
わざわざスーパーで出来合いの弁当なんて買わなかったのに。
「お前。またゲーセンに行ってたんじゃないだろうな?
*この前先生から、放課後の寄り道は禁止だって電話きたこと、
*もう忘れたのか?」
父の言葉を無視して、
部屋の隅に置かれた母の遺影の前へ行く。
そして俺は目を閉じ、心の中で彼女に話しかける。
―― 彼女の遺影の前で、今日あったことを報告する。
それが、俺の日課だ。
けれど今日は、父がそれを邪魔した。
「おい。聞いてるのか。お前のために言ってるんだ……
*お前がそんなんじゃ、母さんだって心配する」
「うるさいな……母さんと話してる時くらい、静かにしろよ」
俺は目を閉じたまま言い返す。
父は俺のことなんて何も知らないくせに、
うるさいことばかり言う……
そんな彼の言葉の全部が、耳障りだった。
どうしてこんなことになってしまったのだろう。
母さんが生きてる頃は………
家族みんな、仲良くできていたのに。
―― ねえ、母さん。
俺は心の中で、母に語りかける。
―― 父さんも、学校のヤツらも……
*誰も彼もに腹が立つんだ……
*皆、眠ってしまえばいいのにね。
その時。ドサリという、大きな音がした。
俺は反射的に目を開けて、音の方へ――
キッチンへと顔を向ける。
父が、身体を投げ出すように倒れていた。
さっきまであれだけ口うるさく喋っていた彼は、
何度呼びかけても返事をすることはなかった。
* * *
父は病院に運ばれた。
医者の説明によれば――
彼はただ、眠っているだけだと言う。
だが、安心することはできなかった。
それは ―― 最近、この街を騒がせる原因不明の病。
身体に異常があるわけでもないのに、
眠りについたまま、ずっと目を覚まさない。
未だ治療方法の確立されていないその病に、
父はかかったというのだ。
翌日の放課後。俺は父の見舞いに、病院を訪れた。
眠りから覚めぬ病。だから彼に会いに行ったところで、
何が起こるわけでもないことは分かっている。
それでも ―― 彼を放っておくことはできなかった。
薬品の匂いがする廊下を進み、彼が眠る病室へ足を踏みいれる。
夕陽の射し込む、仄暗い病室。
そこで ―― 父は立ち上がっていた。
目覚めるはずのない彼が、立っていたのだ。
「父さん!」
病から回復したのだろうか。
俺は不安から解放されたように、彼を呼んでいた。
しかしすぐに、様子がおかしいことに気がつく。
「父……さん……?」
父は病室の壁に向かっていた。
そしてその手に握ったベンで、壁を黒く塗りつぶしている。
まるで、子供がラクガキをするみたいに……
彼が描いている、大きな黒い塊。
それは怪物のようだった。
昔プレイしたゲームに出てくる怪物と似た……
身の毛のよだつような、黒い怪物。
普通じゃない。病院の壁に、ラクガキをするなんて。
俺は何度も父に呼びかけたが、彼は返事をしない。
よく見れば、彼は目を閉じていた。
彼は眠ったまま、ただひたすらに壁を黒く塗りつぶし……
怪物を壁に描きだしているのだった。
父が倒れたのは、2週間前のこと。
彼の身を襲ったのは、最近この街を騒がせている奇病。
突然眠りに落ち、目覚めることができなくなるという、
原因不明の病だった。
母は半年前に亡くなっている。
だから俺は今、家にひとりぼっちだ。
それでも俺は親戚の援助を受けつつ、
いつもどおり学校に通っていた。
そして放課後は必ず、
父の病室へ見舞いに行くことにしている。
俺はそこで……彼が眠ったまま立ち上がり、
病室の壁にラクガキをしているのを見た。
医師は「観察のため」と言って、
ラクガキを消すことはしなかった。
だから今でも、あの怪物のラクガキは残されている。
真っ黒な怪物はいつも、
父を見舞う俺を静かに見下ろしているようだった。
* * *
音楽室から聴こえてくる、クラスメイト達の朗らかな合唱。
クラスごとに参加する校内の合唱コンクールは来月に迫っている。
皆、その練習をしているのだ。
俺は音楽室前の廊下で、
学級員とその取り巻きに囲まれ、問い詰められていた。
「おまえ昨日の練習来なかったの、なんで?」
確かに俺は昨日、クラスで参加する合唱コンクールの練習を欠席した。
けれどそれは父の見舞いに行っていたためだ、と伝えても
彼らは納得してくれない。
他のクラスにも、親が例の奇病にかかっているヤツはいる。
それでもちゃんと練習に来ているのに、
なぜお前だけ練習に来ないのだ……
そんな風に、次々投げかけられる非難の言葉。
もうウンザリだった。
母が死んで、父は眠りから目覚めない。
不幸なのは家の中だけで十分なのに……
学校でまで、こんな目に遭わなければならないなんて。
俺は目を閉じ、口を結んだ。
そして、心の中で叫ぶ。
―― 眠ってしまえ……
皆、長い眠りに落ちてしまえばいい!
不意に、大きな音が聞こえた。
目を開けてみれば、
俺を取り囲んでいた学級員とその取り巻き達が倒れている。
2週間前……父が、倒れた時と同じように。
それだけじゃなかった。
ドサリ、ドサリ、ドサリ。
まるで何かのスイッチが押されたかのように、
廊下を歩く生徒達が、次々と倒れだしたのだ。
さっきまで音楽室から聴こえていた、
クラスメイト達の合唱の声も、今はもう聴こえない。
俺は、慌てて校舎の中を回った。
そして分かったのは、俺以外の全員が倒れているということ。
だが皆、息はしている。
もしかしたら、眠っているだけかもしれない。
突如眠りに落ち、目覚めることができなくなる病……
父と同じ、奇病にかかってしまったのだろうか。
職員室に行き、病院に電話をしたが繋がらない。
不安で、手足が冷たくなってくる。
俺は嫌な予感を抱えつつ、外に出た。
嫌な予感は的中。
街は校舎と同じよう静まり返っていた。
買い物をしていた人、スーツ姿で仕事をしていた人……
皆、地面に伏して眠りに落ちている。
まるで世界にひとりきりになったみたいだ。
俺は暗い森を歩むような足取りで、商店街を目指して進んだ。
人の多い場所へ行けば
もしかしたら、誰か起きている人がいるかもしれない。
そう思ったからだ。
そして商店街のアーチをくぐった時、
まっすぐ続く道の奥に、背の高い影が見えた。
起きている人がいた! そう思い、手を振りかけて気がつく。
あれは、人間ではない。
あれは―― ……・・怪物だ。
昔やっていたゲームに出てきたキャラクター……
そして、父が病室の壁に描いた絵に、
よく似た怪物……
俺は夢でも見ているのだろうか。
だが午後の白い光の中で佇むそれは、確かに怪物だった。
怪物はこちらに気がつくと、
その虫のような羽を揺らしながら、
俺の元へと駆け寄ってくる。
逃げたほうがいいのかもしれない。
だが俺は、恐くて体を動かすことができずにいた。
怪物は俺の前で立ち止まった。
そして俺の顔を覗き込んで言う。
「……夢、食べたい。皆の夢……もう食べ終わった。
*君の夢も、食べたい」
聞き取りづらい、醜く掠れた声だった。
「ゆ……夢?」
「夢食べたい。皆の夢を食べて、人間になる……」
俺はじりじりと後ずさり、怪物から距離を取りながら――
ふと、ある考えが頭に浮かぶ。
この怪物は ―― 皆の夢を食べたと言った。
皆が眠ってしまったのは……この街を騒がせる奇病の原因は。
この怪物に、夢を食べられたからではないのか?
こんなお伽話のようなことを考える自分は、
どうかしているかもしれない。
けれど―――怪物が目の前にいる時点で、
もうどうかしているのだ。
「皆が目を覚まさないのは、
*お前が夢を喰ったからなのか?」
すがるような想いで、怪物に尋ねた。
あの病が……この怪物が夢を喰ったせいで
引き起こされるものならば。
夢を取り戻せば、皆は……父さんは目覚めるかもしれない。
「……返してくれ。夢を……父さんの夢を返せ!」
気づけば俺は、怒鳴るような声をあげていた。
すると怪物は驚いたように走り、逃げ出した。
俺は怪物を追いかけ、走った。
あの怪物から、父さんの夢を取り戻さなければ。
父さんを、眠りから目覚めさせてあげなければ。
そうじゃないと……
父さんのことを大切に想っていた母さんが、
心配するだろうから。
不気味に静まり返った、商店街の大通り。
そこで俺は、怪物を追いかけ、走っていた。
―― 突如として倒れた、学校の生徒達。
彼らは皆、眠りに落ちていた。
その原因は、最近この街を騒がせている病。
眠りについて目覚められなくなる……
俺の父と同じ病だった。
眠りに落ちたのは学校の生徒達だけじゃない。
街中、俺以外の全員が眠りに落ちていたのだ。
そして、起きている人を探し、
商店街の奥まで辿り着いた俺が出逢ったのは、黒い怪物。
まるでゲームの中から出てきたようなその怪物は話した。
「皆の夢を食べたのだ」と。
―― きっと皆が眠りに落ちたのは、
この怪物に夢を喰われたせいだ。
そう信じた俺は怪物に夢を返すよう迫ったが……
怪物は何も言わずに、俺の元から逃げ出してしまった。
だから今、俺は怪物を追いかける。
逃がすわけにはいかない。
アイツには、父の夢を返してもらわなければならないのだから。
道端で眠る人々を踏まないよう、商店街を走り抜ける。
怪物は猛スピードで駆け抜けては、
時折立ち止まり、こちらを振り向いた。
あの怪物が何を考えているのかは分からない――
だが、まるでこちらを誘っているようだ。
そして怪物は、商店街の外れにある、
古びた建物の中へと入り込んだ。
古びた建物 ―― それは俺がいつも通う、ゲームセンターだ。
俺は怪物の後に続き、ゲームセンターの入口をくぐった。
商店街の静寂は遠ざかり、様々な筐体が放つ音が、
いつもより鮮明に鼓膜に迫ってくる。
俺は怪物の姿を求め、慎重に歩みを進めていく。
そして、埃っぽい室内のいちばん奥。
忘れ去られたような暗がりの中にある、
リズムゲームの筐体――
その前で、怪物は静かに立ち尽くしていた。
それは、俺が幼い頃に母と遊んだリズムゲーム。
そして半年前、母が亡くなった日からずっと……
俺はこのゲームに母の面影を求め続け、何度も遊んできた。
ネオンのように光を放つスピーカーから放たれる、
ポップなシンセサイザーの音。
怪物は明るく光を放つディスプレイを、
小首を傾げながら見つめていた。
その姿はどこか人間のようで、
怪物らしい恐ろしさは感じられなかった。
「……楽しいぞ、そのゲーム」
気付けば俺は、怪物に声をかけていた。
怪物は俺を見て小さく頷くと、
おそるおそる筐体のディスプレイに触れた。
右も左も分からないと言ったような、
不器用な手つきがもどかしい。
俺は怪物に、ゲームの操作方法を教えてやる。
まずは筐体の中にコインを……
ふたりで遊ぶ時は、2枚。
それからディスプレイに表示される曲の一覧から、
リズムゲームを遊びたい曲を選ぶ。
……怪物に、人間の音楽は分からないだろう。
俺は怪物の代わりに曲を選んでやる。
よく、母と一緒に遊んだ曲を。
ディスプレイが激しい光を放ち、ゲームが始まる。
軽快な音楽に合わせて、
ディスプレイ内を音符のマークが流れ落ちていく。
そのマークのタイミングに合わせて、
俺達は足元のパネルを踏んで踊るのだ。
ディスプレイを見つめながら身体を動かすと、
身体の底から楽しさが沸き上がってくる。
不思議だった。
怪物が隣にいる ―― こんな状況でも、
純粋にゲームを楽しんでいる自分が。
俺は踊りながら、ちらりと隣の筐体に目をやる。
怪物は戸惑ったように、
あたふたと不器用なステップを踏んでいた。
「……へたくそ」
恐ろしい見た目をした怪物が、
ピエロみたいにヘタクソなダンスを踊っている……
俺は思わず笑ってしまった。
すると怪物はどこかむっとしたように、
一生懸命に足を動かした。けれど一生懸命になればなるほど
リズムを見失い、おかしなステップになっていく。
そんな怪物の不器用さを見ながら――
俺は何か、胸に懐かしいものが込み上げてくるのを感じていた。
気付けば俺は、ステップを踏む足を止めていた。
ゲームを途中で投げ出したことなんて今まで一度もなかったのに、
今は隣で踊る、怪物の姿から目を離すことができなかった。
へたくそなステップ。
けれど楽しそうなその足取り。
子供よりも夢中になる姿。
そのどれも、見覚えがある・・・・・
俺は……知っている。
目の前にいる黒い怪物の正体を、俺は知っている。
「……母さん?」
俺は思わず、怪物にそう呼びかけていた。
一体俺は何を言っているのだろうと、
自分で自分を笑いたくなる。
だけど ―― 今、目の前にいるこの怪物が、
母に思えてならなかった。
俺は幼い頃、こんな風に踊る母を何度も見た。
そんな彼女との思い出を何度も胸の内に蘇らせながら、
今日まで生きてきたのだ。
怪物が、ステップを踏む足を止める。
そしてその瞳のない顔を、俺へと向けた。
長い沈黙があった。
ただシンセサイザーの音だけが、
俺たちの間に横たわっている。
やがて、怪物の口が開かれる。
怪物は枯れた声で、呟いた。
俺の名前を・・・
母さんがつけてくれた、この名前を。
街中の人々が、眠りについた。
父も、学校の生徒達も、道を行きかう人々も――
俺以外の全員が。
それは突如として眠りに落ち、
目覚めなくなる奇病が原因だった。
そして俺の目の前に現れたのは、真っ黒な怪物。
怪物は話した。「皆の夢を喰った」と。
皆が目覚めなくなったのは、
きっとこの怪物が皆の夢を喰ったせいだ――
そう考えた俺は、走り去る怪物を追いかけた。
怪物が逃げ込んだのは、古びたゲームセンター。
そこでリズムゲームを踊る怪物の姿を見て――
俺は、母のことを思い出していた。
半年前に亡くなった母のことを。
俺は思わず、怪物に「母さん」と呼びかけた。
そして怪物は――俺の名前を呼んで応えた。
逢ったこともないはずの怪物が、
俺の名前を呼んだのだ。
母さんがつけてくれた、この名前を。
怪物は、俺の名前を繰り返し呟いた。
何かを思い出すように、何かを確かめるように……
それからゆっくりと俺の元へ歩み寄ると、
その大きな手で俺の頬に優しく触れた。
「……人間に、なりたい。
*思い出したの、その理由を……」
怪物はそう言った。
「皆の夢を食べれば、人間になれる。
*もう一度、あなたに逢える……だから」
怪物は ―― 母は話した。
人付き合いが苦手で、頑固で衝動的な俺のことを遺して
死ぬことが、心残りでしかたなかったこと。
ずっとずっと俺のことを心配して……
気が付いたら、怪物の姿になっていたことを。
俺は母に抱き着いていた。
冷たそうに見えていた、その鎧のような身体は温かかった。
「母さん……」
逢えて嬉しい。
こんな嬉しいこと……もしかしたら、夢なのかもしれない。
いや、夢でもいい。
ずっとこのままでいたかった。
けれど、そんなことを言えば、
母は今よりもっと俺を心配するだろう。
だから彼女に教えてあげなければ。
俺はもう ―― 母さんがいなくても、
ちゃんと生きていけるのだと。
「母さん。もう大丈夫。
*だから。皆の……父さんの夢を返して……」
そう告げると、
母は何も言わずに俺を抱きしめていた腕をほどいた。
見れば彼女の黒い体は、淡い光を放っている。
それは空気の中に溶けてしまいそうな、柔らかい光だった。
もしかしたら彼女は、これから消えていくのかもしれない……
そう思ったら、視界が滲んだ。涙が零れそうだった。
それから母は消えそうな手で、
筐体のディスプレイを操作した。
シンセサイザーの音が弾け、リズムゲームがスタートする。
彼女は何を言うでもなく、足元のボタンを踏んで踊り始めた。
その消えそうな体で、楽しそうに不器用なステップを踏みながら。
母がこちらを見る。怪物になったその顔からは、
表情を読み取ることはできない。
けれど一緒に踊れと誘われているようだった。
俺は音楽に合わせて、彼女とふたり並んで踊った。
幼い頃と同じよう、無邪気に、全力で。
消えていく彼女の身体を見ると、寂しくてたまらない。
それでも、やっぱり、母と一緒に踊るのは楽しかった。
やがて、音楽が終わる。
踊る足を止めて隣を見ると、母は消えていた。
あの怪物の姿はもう、跡形もなくて。
今までのは全部夢だったんじゃないかと思った。
けれどディスプレイに表示されるふたりぶんのスコアが、
確かに母がここにいたことを教えてくれた。
* * *
ゲームセンターの外に出ると、
さっきまで道端で眠っていた人たちが
目を白黒させながら起き上がっていた。
きっと怪物が ―― 母が、皆の夢を返してくれたのだろう。
父もまた、無事に目を覚ましていた。
俺が病室を訪ねた時、彼は壁に描かれたラクガキを
掃除している最中だった。
ラクガキ ―― 父が眠りながら描いた、怪物の絵だ。
そういえばこの絵は、怪物になった母によく似ている。
「俺が眠りながらこんな絵を描いたなんて、
*なんだか気味が悪いなあ」
父はそうぼやいた後に、
「だけど」と付け足した。
「昔、こんなお伽話を聞いたことがある。
*死んだ人は夢喰いの怪物に
*生まれ変わることがあるんだって……」
彼はそこで気恥ずかしそうに言葉を止めた。
けれど、彼が言いたいことは分かっている。
きっと、亡くなった母は夢喰いの怪物になって
俺たちに逢いにきたのだ……
そういうことだろう。
そして俺は知っている。
本当に、母は夢喰いの怪物になって、
俺達に逢いに来てくれたことを。
俺はそれを父に伝えようか迷ったが、
言わないことにした。
実のところ、あの出来事が夢か現実かも分からないのだ。
それに……誰かに話した途端、
夢に変わってしまうような気もした。
それから俺達はふたりで一緒に、
壁のラクガキ掃除に励んだ。
「そういえばお前……俺が入院してるからって、
*部屋を散らかしてるんじゃないだろうな?」
はじまった。いつもの、父のうるさい小言。
だけど今日だけは言い返すのをやめておこう。
喧嘩なんかしたら、また母が心配するだろうから。
俺は、消えていく怪物のラクガキを見つめながら想う。
母が亡くなった寂しさは、
これからもずっと続くかもしれない。
けれど母はきっと、今も夢喰いの怪物となって
誰かの夢の中で生きていて。
遠くから、俺のことを見つめている。
だから俺は、歩き続けなければならない。
母を心配させないよう、前を向きながら。
「夢喰いの怪物・・・・・・本能に従って人間の夢を喰らい、ヒトの姿を望
「む種族。けれど彼は、自分が人間になる事よりも、あの子を人間
「に戻す事を望んだの」
「本能に逆らうなんて粋ですねえ! これぞ、愛でございます」
まったく、嫌になっちゃう。運送屋ったらいつもママを食ったような話し方をするんだから。代理さんは代理さんで「・・・・・・愛っス」だなんて言ってる。はあ。ママ、ふたりと話すのは苦手だわ。
「大体、怪物達は、何故人間になりたいんですかねえ。強靭な肉体
「を持った彼等は、人間などより、余程立派な生物に思えますが」
「・・・・・・そんなこと言って。貴方、色々知っているのでしょう?」
「いやはや、貴方程ではございませんよ。怪物について、もっと
「色々じーっくり私に教えてくれてもいいのですよ?」
「・・・・・・教え・・・・・・てっス」
「あらあら。そんな目で見つめられたら、ママ困っちゃうわ」
・・・・・・確かに、ママは運送屋よりも怪物達について詳しいわ。だからこそ、分かるの。彼があの子の為にとった行動が、どれほど奇跡的な事か。そして、どれほど運命的な事か。
ま、運送屋には何も教えてあげないけれど。
「おい、運送屋。アイツはまだ来ないのか?」
アイツアイツってうるせぇな。
・・・・・・と心の中で毒づきながら、俺は努めて恭しい声色を作る。
「まあまあ、ご心配召されますな・・・・・・」
こいつ、旅の目的忘れてんのか?
ガキと遊びに来てんじゃねえんだぞ。でも一応リマインドはかけとくか・・・・・・仕事だし。
「貴方様は、お嬢さんの夢を喰らい尽くす。そして人間になる」
「ああ、わかってる」
「さすがでございます、レヴァニア様」
・・・・・・ったく、でくの坊をおだてて働かせるのも楽じゃねえな。
いいか忘れるなよ、あんたは俺の為に行動するんだ。俺に利用され、
搾取されることだけがお前の存在価値なんだ。
・・・・・・と、心の叫びはこのへんにして、面倒くせえが今日もお仕事モードいっちゃいますかねえ。俺の愛すべき愚者達の為に・・・・・・
「さて・・・・・・そろそろお嬢さんがやって来ますよ」
「早くしろ」
「それでは・・・・・・・・・・・・ほいさっと!」
陰気な怪物「……この夢…………まず…………い………………」
軽薄な怪物「こっちはまあまあ悪くねぇ。俺のは当たりだ!」
胡乱な怪物「ウルサイゾ貴様、味ナンテドウデモイイダロ」
軽薄な怪物「固いこと言うなよ。なあ、お前もそう思うだろ?」
陰気な怪物「……あんたは……うるさい…………」
胡乱な怪物「ソレミロ。ワカッタラ貴様ハ黙レ」
軽薄な怪物「あぁやだやだ。これだからお前らは根暗だって……」
胡乱な怪物「根暗デ結構ダ。ナア、オ前モソウ思ウダロ?」
陰気な怪物「……おれ…………明るく……なりたい…………」
胡乱な怪物「フン、貴様ニハ無理ダ」
陰気な怪物「……どうすれば…………明るく……なれる……?」
軽薄な怪物「人間になれた後の、楽しい未来を想像してみるとか」
陰気な怪物「……楽しい……未来…………?」
胡乱な怪物「人間ニナッタラ、何ガ楽シインダ?」
軽薄な怪物「よく考えたら、俺にもわからねえな」
胡乱な怪物「ジャア何故……我々ハ人間ニナリタインダ?」
軽薄な怪物「それもよくわからねえ」
陰気な怪物「……何の為に……おれ達……生きてるんだ……?」
冷たい石造りの床を彩る、紅の落葉。その上をふたつの影が行く。
黒き怪物と、彼の少し後ろをついていく少女。その影だ。
「あのね、カイブツさん。わたしね、
「カイブツさんが人間になったら、一緒にやりたいことがあるの」
少女が、怪物の背に声をかけた。
怪物は振り返らないまま「なんだ」と答える。
「そのいち。一緒にお花を見ること。
「そのに。一緒にケーキを食べること。
「そのさん。一緒にお勉強して、面白いことをたくさん知るの!」
「・・・・・・くだらん」
怪物は、少女の提案を一蹴する。しかし ――
少女の少し先を足早に進んでいた怪物の足取りは、
次第にゆるやかになり、やがて立ち止まる。
そして少女を見下ろし、言った。
「いいから、もっと夢を喰わせろ。
「・・・・・・そうしたら、少しくらいは付き合ってやってもいい」
ぶっきらぼうな、怪物の言葉。少女の笑顔が、ぱっと花開く。
「うん、約束だよ!」
砂埃に塗れた石畳の上で、少女が閉ざされた扉を見つめている。
物言わぬ少女が胸の内に抱えるのは、黒き怪物のこと。
先ほど少女とママの前に現れ、すぐに走り去った怪物――
少女はママと共に怪物を追いかけたが、見失ってしまった。
きっと怪物は、閉ざされた扉の向こうに行ってしまったのだろう。
少女は意思に満ちた瞳で、怪物のことを想う。
―― 黒き怪物は・・・・・・あの子は。今、絶望の縁にいる。
ニンゲンの感情が分からない自分には、
あの子の痛みを本当の意味で理解する事はできないかもしれない。
それが、己を呪いたくなる程に悔しい。
けれど、あの子の友達になって・・・・・・
傍にいてあげることくらいはできるはずだ。
「気持ちは分かるけど・・・・・・ ね?」
少女の背を、ママが促す。そうだ、立ち止まっている暇はない。
まずは歪められた記憶の物語を修復し、武器を集めなければ。
そして失った欠片を取り戻そう。すべてはあの子を救うために ――
「カイブツさん、人間にはなれなかったの?」
「・・・・・・いいんだ」
戦いの中で、互いの想いをぶつけあった末、
あるべき姿に戻った怪物と少女。
・・・・・・手を繋いでいた。光の中で、二人。
少女の手のぬくもりを感じながら、怪物は想う。
―― ずっと、ニンゲンになりたいと思っていた。
「夢喰いの怪物」としての本能に従って、夢を喰らい続けてきた。
ただそれだけが、己の生まれた意味だと信じていた。
しかし今、気が付いた。
彼女の笑顔を見て、気が付いたのだ。
彼女と友達になること。
そのために、俺は生まれてきたのかもしれない。
ずっと探していた答えが、ようやく見つかった気がする。
© SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
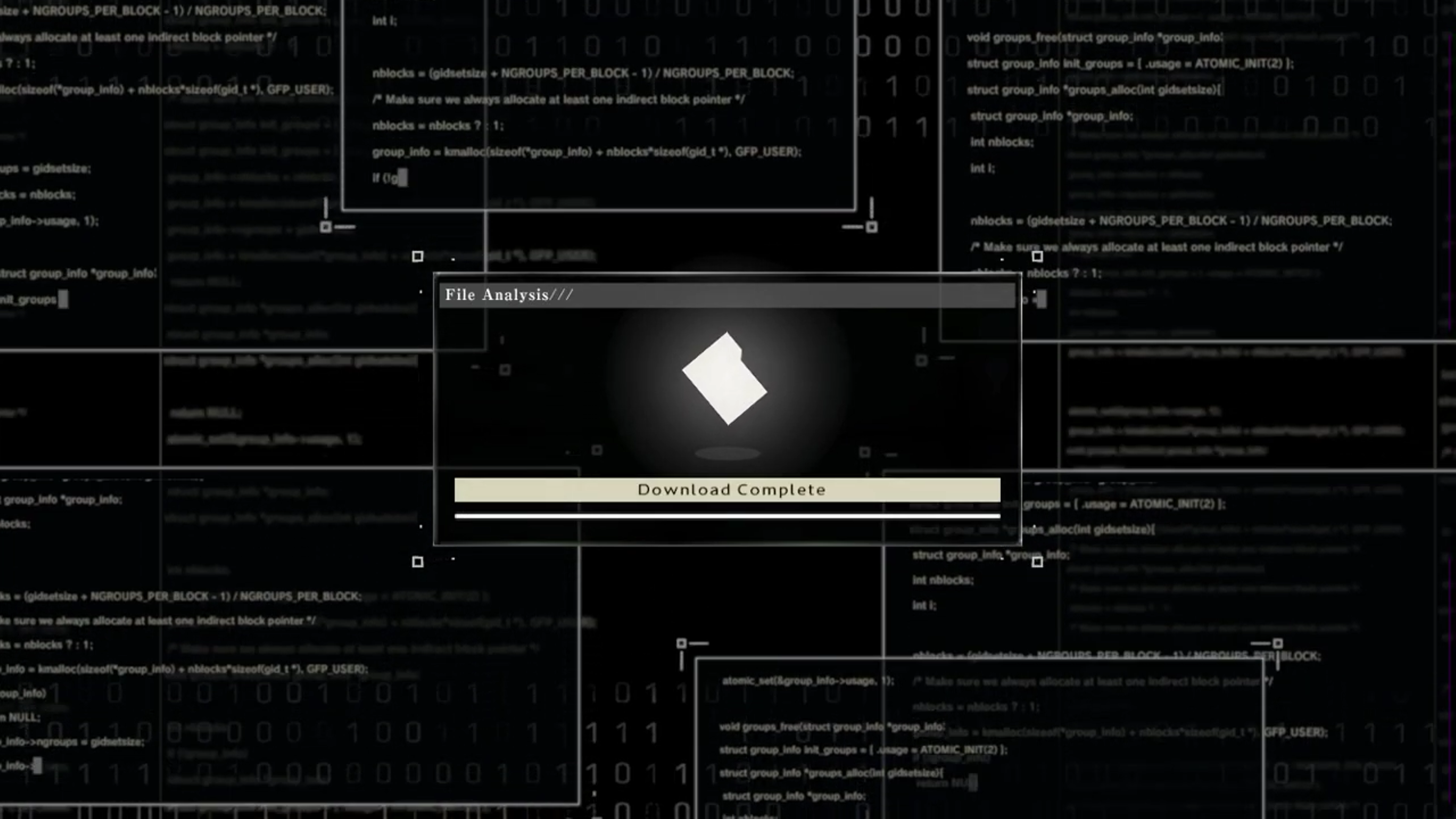





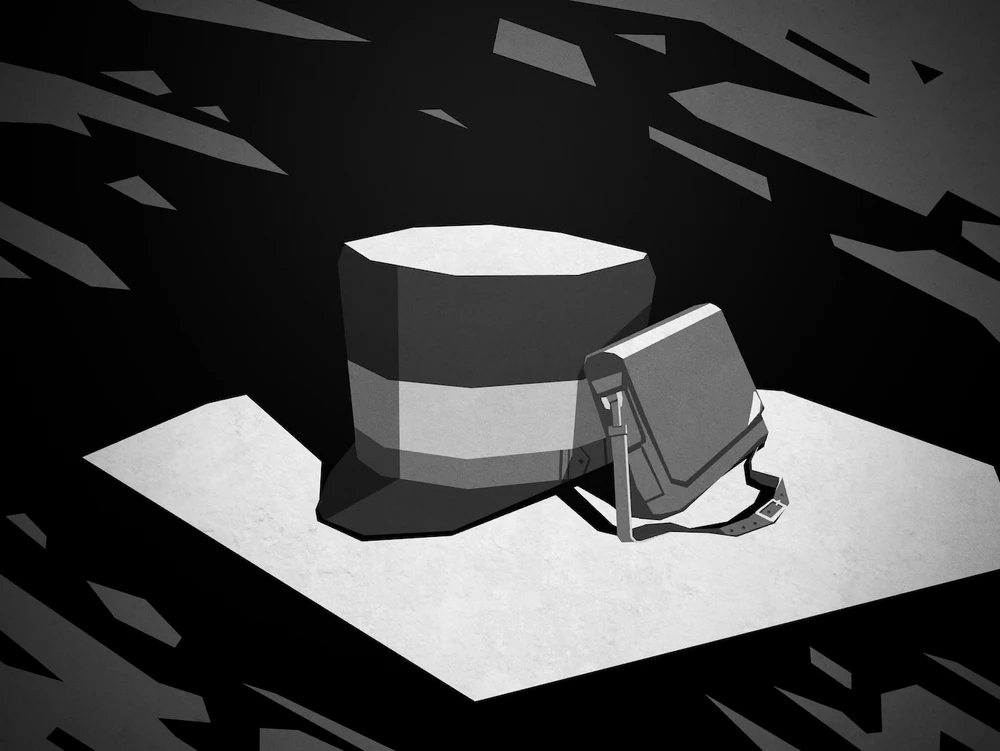






コメント