シークレットストーリー
遥か遠くから、まだひんやり冷たい潮風が
王宮にまで流れてくるある日の朝方。
寝台から抜け出し、ぼんやりと窓の外を眺めていた私のもとに、
急な報せがやってきた。
告げに来たのは、娘直属の侍女だった。
彼女は、沈痛そうに声を震わせる。
「女王様……姫が、海に出てしまわれました」
「教えてくれてありがとう。
*……これで、ようやく清々するわ」
私は、この国を治める女王。
そして、姫は私の娘である。
こうなるであろうことは、察していた。
娘が船乗りの少年と駆け落ちし、国を去るであろうことは。
そして、それを私は望んでいた。
他国の王に嫁がせても戻ってきた娘が、
この国から出て行ってくれるのならば、何も問題はない。
いや、むしろ御の字といっていいだろう。
偶然に出会った儚い希望にすがらせ、
自分から国を捨てる覚悟を持ってもらう。
その計画が、私の意に沿う結果をもたらした。
静かに去っていく侍女を背に、私は再び窓の外を見やる。
私が育て、発展したこの国の賑わい。
強靭な兵が集まり、国力を増した我が国。
―― ここまで国を守るのは、本当に大変だった。
あの人と後に王配となる彼と出会ったのは、
私が今の娘と同じくらいの年齢のときだっただろうか。
近隣でも特に貧しい小国であったこの国は武力も弱く、
常に他国からの侵略に晒されていたが、
人々は優しく、その心は豊かだった。
繋がりを重んじ、経済的な弱者にも温かかった。
そしてあの人はそんなこの国を心から愛する、
貧民出身の青年だった。
彼は親のいない子ども達にも愛情の施しを与え、
身よりのない老人達にも労りの手を伸ばす。
そんな彼を誰もが頼り、誰もが好いていた。
私は王室の行事で街を訪問したときにその様を見て、
彼の在りかたに惹かれた。
彼とひととき語り、その低くたくましい声に耳を傾けた。
王宮に帰ってからも、私は彼を思い出した。
寝台に潜り、瞳を閉じても彼の姿が脳裏に浮かんだ。
そしていつの間にか私は、朝も昼も夜も常に、
彼のことを想うようになった。
要するに私は―― 彼に恋をしてしまったのだ。
それは私の初恋でもあった。
だが当然の如く、私の周囲はその恋に反対した。
あまりにも距離が遠い、身分違いの恋。
彼と会うことは禁じられ、
一時は部屋に閉じ込められそうになった。
そうやって、私の心を冷まそうとしたのだ。
―― そのような逆境が、私を燃え上がらせた。
私は毎晩のように部屋を脱け出し、彼と逢瀬を重ねた。
裸足で道を駆け、転んで膝を擦りむいても、
彼に会いたくて一心不乱に走った。
身分の壁を越えてでも恋を貫く私に、彼も応えてくれた。
傷だらけの私を抱き締め、誰よりも慈しんでくれる。
―― 誰も、私達を止めることはできない。
その恋は、国中を巻き込む大恋愛となった。
私と彼がどれだけ破天荒な物語を生んだか、
それを語るには語り部がどれだけいても足りない。
やがて紆余曲折を経て私達は結ばれ、
親族にも認められると女王と王配 ―― 夫婦となった。
以来私はとても幸せで、彼も私も満ち足りていた。
それだけで、充分だった。
―― はずなのに。
こんなにも、私達は愛し合ったというのに。
深く強く、一生を捧げて私は彼を想ったのに。
夫は……
大好きだった彼の心は、その日から変わってしまった。
私だけに向けられていた視線が、あちらに逸れた。
私が授かった、新たな命に。
私が、あの子を生んだ日から。
夫が、我が娘と会った日から。
そう。
娘が、私から彼を ―― すべてを奪ったのだ・・・・・
この国の姫である娘が、
誰とも知れない少年と一緒に国を捨て、
そして海に出た。
―― これでもう、娘の顔を見なくてすむ。
女王である私は安堵し、この結果に満足していた。
椅子に深く体を預け、くつろいで瞳を閉じる。
いつかのあの日のように、夫を思い出す。
朝、目覚めたばかりの私の髪に触れ、
私の耳元で、君の髪はいつも美しいと褒めてくれた。
その低く甘い囁きが、好きだった。
朗らかに私を優しく見つめ、笑いかけてくれる。
その温かで柔らかい瞳が、大好きだった。
私の一挙一動に、夫は反応してくれた。
あれだけ人に好かれていた夫の好意が、私だけに向く。
王族であることなどより遥かに胸が高鳴る、優越感。
最愛の人の愛を独占できる、妻にだけ許された充足感。
彼もきっと、同じことを感じていただろう。
王宮に入ってからは清く正しく優れた王配となった彼に、
周囲も文句を言わなくなった。
誰にもこの営みを、邪魔できない。
そう思っていたはずなのに、
思いも寄らぬ理由でその生活は破綻した。
きっかけは、私の出産だった。
元気いっぱいに泣き声をあげて、
国民の祝福を受けて生まれてきた、私と彼の娘。
健やかで、頑丈で、とても私と彼に似た我が子。
それ以来、私が独占していた夫の声も、夫の視線も、
すべてが娘に注がれることになった。
夫はいつも娘に首ったけで、
私の髪にも、私の顔にも、見向きもしない。
私だけが、想いを与えられず。
娘だけが、夫の寵愛を受ける。
どれだけ耐えがたく、虚しい日々だったか、
理解してくれる者は一人もいなかった。
何よりも夫が最も、私の苦しみをわかっていなかった。
―― あれだけ、私の心を悟ることが得意だった夫が。
娘の心を育てることだけに、苦心していた。
次の子を私が生めば、夫も育児に飽きるだろうか。
そう思ったこともあったが、
結局私と夫は、第二子を授かることはなかった。
そうして娘はすくすくと、明るく朗らかに育った。
しかしそんな中、夫は重い病に罹ってしまった。
病床に臥せ、咳き込んでいるだけで過ぎていく日々。
夫はいつも痛みのせいで朦朧としていた。
強がって口には出さなかったが、猛烈に苦しんでいたに違いない。
私は献身的に自らの手で看病した。
―― 夫の心変わりに期待していなかったかと言えば、
嘘になる。
彼に水を飲ませるのにも、彼の体を拭くのにも、
あのころ以上に愛を込めた。
私の想いは、日々強まっていったと思う。
だが夫の心が、再び私に向くことはなかった。
夫は床の中で毎日、私に尋ねる。
「今日、あの子は何を覚えた?」
「今日、あの子は何を食べた?」
「今日、あの子は元気だったか?」
娘の日常、娘の成長、娘の体調、そればかり。
私への感謝の言葉も時にはあったが、
その言葉に重みがないことは誰よりも私に伝わった。
―― 娘への痛々しいほどに強い気持ちは、
こんなにもひしひしと伝わってくるのに。
夫への愛は増し、娘への憎しみは募る。
自分が歪んでいくのがわかったが、
私の意思ではどうしようもなかった。
そうして看病の日々がはじまってから、
太陽と月が千と幾つか入れ替わった、ある日の夜。
夫は私の看病の甲斐もなく、あっさりと死んだ。
「この国の民と娘のことを、よろしく頼む……」
最期の言葉を、私に遺して。
私のことには、一切触れず。
私との思い出に、まったく思いを馳せず。
私の一抹の希望はそのときに砕かれ、
今も私を苦しめる。
今にして思えば、彼は自身を蝕む病に
ずっと早く気付いていたのかもしれない。
娘への愛情の注ぎ方も、そうであったなら納得はできる。
しかし、納得はできても許せはしないし、
この娘への憎しみが消えることはない。
それでも私は決意を胸に、立った。
夫が遺した言葉の通り、この国を守ろうと。
―― そのためには、
娘を利用することも、厭わないと。
国と娘のことだけを案じ、死んでいった最愛の夫。
「この国とあの娘のことを、よろしく頼む……」
夫が遺した、私への願い。
私は国を代表する女王として、
夫が愛したこの小さな国を育てると、心に誓った。
それまで疎かった政治を学び直し、
経済を動かし、兵を増やし、国力を上げる。
他国からの武力的な介入にも、太刀打ちできるように。
私は国のため、心を鬼にして邁進した。
国を強くするためならば、娘も利用した。
列強国に比肩する兵力を従える他国の王に、
娘を捧げて国交を結ぶ……
典型的な、政略結婚。
幸いといったところか、娘は私を少しも疑っていなかった。
一方で私は娘が、嫁ぎ先で王の気分を損ね、
殺される結果になろうともまったく構わなかった。
いや、むしろ殺されてほしかった。
私の視界に触れないところで。
あれだけ娘を疎み、憎らしく思おうとも、
私は自ら手を下すことだけはできなかった。
何故ならあの娘は ―― 似すぎていたから。
心から愛した夫の、綻んだ瞳。
大好きだった夫の、朗らかな笑顔。
そして夫が毎朝のように褒めてくれた、
私と同じ、流れるような美しい髪。
―― 娘への憎悪は、本物だ。
妬ましさも、疎ましさも。
いくら美辞麗句を並べようとしても、その感情に嘘はつけない。
だが ―― こんなことを言っても信じてもらえないだろうが、
夫の面影を残し、私の血を継いだ我が娘を、
私は愛してもいた。
身勝手すぎると思われても、仕方ないだろう。
それでも矛盾すべき二律背反の心は、
私の中でせめぎ合いながら両立していた。
だからこそ、自ら娘を殺すことができなかった。
だからこそ、自らの手の及ばぬ場所で娘が死ぬことを望んだ。
複雑にして怪奇な心境だが、自分の愛を殺さず、
憎しみを通すには、それしか思いつかなかった。
これで娘の笑顔も、死に顔も、見なくてすむ。
―― しかし、娘は当然のような顔で、帰ってきた。
結婚生活を見限って、
この国を思い出し、
私への愛を強く、思い出し。
昔と同じ、夫によく似た笑顔と瞳で、
今も娘は私を見ている。
娘は生まれて以来、
一度も私に憎まれていると思ったことはないだろう。
私がただ夫を愛し、ただ娘を愛していると――
母の慈愛を、純粋に思い込んでいる。
そんな純粋な顔で、娘は。
「会いたかった、お母様」
―― 私に、甘える。
私にすがる。
それがどうしても、耐え難かった。
憎悪だけであれば、こうも辛くはなかっただろう。
だがその笑顔が、大好きな夫に似ているが故に、
その可愛らしさを私も理解できるが故に、
夫からの愛を彼女に奪われた理由も、私はわかってしまう。
この先どう生きようとも私は、
この笑顔に付きまとわれ続けるのか。
これだけこの国を大きくすることに専念しても、
神は私に、このような罰を与えるのか。
許せない。
せめて、その笑顔さえ奪えれば、
夫の面影さえ掻き消せれば、
少しは楽になれるだろうか?
「私はお前に会いたくなどなかった」
死すら望んでいたと、私は娘に冷たく言い放った。
娘の表情が凍り付いていく。
願わくば永遠に。
その笑顔を私に向けぬよう……
政略的な目的で輿入れさせた娘が、しかし戻ってきてから、
また幾つもの太陽と月が入れ替わった。
あの日、娘を傷つける言葉を放ってから、
私の望み通り、娘が笑顔を見せることはない。
そうして私は娘に夫の面影を感じずに済み、
以前よりは平穏な心情を得た。
だが、それでも同じ王宮内に娘が暮らし、
息をしているのかと思うと、
苦痛を忘れることは決してない。
「笑わない姫」の噂が国中に溢れてもなお、
私は満足できなかった。
そこで私は、次の手を打つことにした。
娘がこの王宮を出て行くには、
やはり相手がいなくてはならない。
だから私は、お触れを出した。
「笑わなくなった姫を笑わせた者に、姫をやる」と。
大きくなったこの国で王族と血縁を持てるのならば、
この先の生活で困窮することはないだろう。
そう考えた様々な国から、男達が娘の前に詰め寄ってくる。
誰でもいい。
娘が笑える相手であれば、娘も文句を言わないだろう。
その中に高貴な血筋の男がいれば、王宮にも利益がある。
また、娘を目的に集まる人流も、経済を活性化させるだろう。
私にとって、困るようなことは何もなかった。
しかし娘は、何者が来ようともまったく笑わなかった。
――娘の絶望は、それほど深かったようだ。
娘の心からは笑いだけではなく、喜怒哀楽、
すべての感情がなくなってしまったかのようだ。
娘の後ろから頼りにならない男達を眺め、
私の心もささくれ立ってくる。
――この目論みは、うまくいかないのか。
私が暗澹たる心持ちになっている中、
ある日、娘の眼差しが一瞬だけ昔の眼差しに戻った。
それは、やってきたとある男……というにはまだ若い、
少年の話を娘が聞いていたときだった。
船乗りを名乗る彼の言葉に、娘が明らかに惹かれている。
心が、揺れている。
他の者は気づかなかったようだが、
本人ですら気付いているか怪しいが、あの瞳は確実にそうだ。
あれは私を愛してくれた、私だけを見てくれた、
夫の眼差しと同じものなのだから。
そして、しばらくして――
つい先ほど、娘が駆け落ちをして海に出たという報告が、
娘の侍女から告げられた。
――かつて私が、貧民の青年を見初めて部屋を飛び出したように。
娘が彼との結婚を望んだとしても私は断らなかっただろうが、
駆け落ちをして自ら縁を切ってくれるのならば、
これ幸いと見逃すほうが簡単で、都合がいい。
「これでやっと、あの笑顔から解放された」
私はようやく自分を取り戻したことを喜び、
王宮の奥で一人笑った。
もう何も、私を呪縛するものはない。
やりたいように、生きたいように過ごすだけ。
これまでの苦難の日々を思い出しながら、
私は窓から自分の国を見下ろす。
――そこに見えるのは。
巨大に、膨れ上がった街。
血気盛んな若者が溢れ、
商人は堂々と人々を欺き、
軍事に携わる者達は、常に他国への侵略を策謀している。
弱者を労わる視線こそないが、
弱肉強食の理は、この国を大きく成長させた。
この国は――強く豊かだ。
夫にも、夫の面影を残した娘にも、
夫の愛した国の面影にも、
私はもう、出会うことはない。
この国は、他国が羨む理想的な国家になった。
私は確かに、責務をまっとうしたのだ。
しかし。
私が愛したものは。
あの人が愛したものは。
そこに、一つも残っていなかった。
もうどこにも、ありはしないのだ……
運送屋 「人を貶めたり、人の心を弄んだり、■■ですね!」
「 と、声を大に主張する運送屋。
「 それに対し、黒いママは困ったように言う。
ママ 「それはそうかもだけど・・・・・・・それ、あなたが言う?」
運送屋 「どういう意味です? ■■に■■って言って何が悪いんで
「 すかね? 占いの力は本物だったみたいですけど、それを
「 悪用するなんて言語道断。まぁ、信じる方にも問題はある
「 と思いますけどね? 占いなんてものに細るような輩がい
「 るから、占い師なんて胡乱な輩も蔓延るんですよ!」
「 止まらない運送屋に、呆れる黒いママ。
ママ 「私、この人とは上手くやっていけなさそう……」
赤さん 「彼、今朝の占いで、運勢最悪だったみたいだよ」
ママ 「占いは私も好きだけど、影響されすぎるのも考えものって
「 ことかしら?」
○月×日 はれ
今日は、女王さまにおよばれしました。
としが近いからというりゆうで、なんと!
ひめさまのお世話がかりに、にんめいされたのです。
わたくしは、こうえいだなと思いました。
ひめさまは、かみの毛はふわふわだし、目はまんまるで、
とってもかわいいです。
さっそくひめさまは、女王さまのうしろにかくれながら、
「いっしょに、ご本よんで」と、わたくしに言ったので、
ご本をよんでさしあげました。
たのしそうにゆれながら聞くひめさまは、
それはそれは、かわいかったです。
これからお世話がかりとして毎日いっしょだと思うと
ゆめのようだなと、心がはずみました。
○月×日 くもり
今日も、ひめさまが王宮をぬけ出しているみたいです。
お外は危ないので、わたくしは心配です。
近ごろは、ご注意さし上げても
いたずらっぽく笑うばかりで、聞いてはくださりません。
わるいとは思いつつも、
女王さまにも告げ口をさせていただきました。
しかし、女王さまからは放っておくよう言われてしまいました。
ひめさまには、お父上さまがいらっしゃいません。
お母上さまでいらっしゃる女王さまからも、
気にとめていただけていないご様子。
ああ、かわいそうな、ひめさま。
わたくしが、ひめさまを守ってさし上げなくては。
わたくしだけが、ひめさまを。
○月×日 雨
突然、姫さまが他国の王の元へ輿入れされてしまわれました。
差し出がましいと思いつつも、
わたくしは、姫さまに仕え続けることを願い出ましたが、
女王さまには聞き入れてはいただけませんでした。
どうしてでしょう?
わたくしは今まで一番姫さまの近くにいて、
一番姫さまを想っているというのに。
今日、女王さまからは、姫さまのお部屋を片付けておくよう、
言いつけをいただきました。
そうですよね。いつか帰ってくるかもしれません。
お部屋は綺麗にしておきましょう。
姫さまの寝台。少しだけなら、いいですよね?
○月×日 快晴
なんということでしょう!
先日、姫さまが輿入れされた国から帰って来られました!
でも、以前のような笑顔を見せてはくださりません。
女王さまはそんな姫さまを見て、
姫さまを笑わせた者に姫さまを興入れさせる、
というお触れを出されました。
再び、姫さまと離れ離れになるなんて考えたくもありません。
笑顔を見せない姫さまも凛としていて素敵ですが、
以前のように、無邪気に笑う姫さまのお姿も拝見したいです。
でも、そうすると姫さまと再び離れることになるでしょう。
もし姫さまがお笑いになっても、
お相手がいなければ輿入れの話はなくなるでしょうか?
それならば、わたくしは。
姫さまに入れ替わりをお願いされました。
少年の自分への想いを確かめるのだと。
どうしてわたくしに、姫さまの願いを断ることができるでしょう?
しかし、あの馬鹿な少年はそれに気づかず、
わたくしを姫さまと勘違いしたまま、王宮を出ました。
手を汚すまでもない。姫さまも目を覚ましてくださる。
そう確信しておりましたが、
姫さまは少年と一艘の小船で海に出てしまわれました。
わたくしはそれを止めることができませんでした。
絶望と愉悦が混ざったような姫さまの形相に、
動けなくなってしまったのです。
あんなのは、姫さまではありません。
わたくしのかわいいかわいい姫さまは、そうこんな笑顔。
この鏡に映ったような、この笑顔こそが
わたくしのかわいい姫さまなのです。
© SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
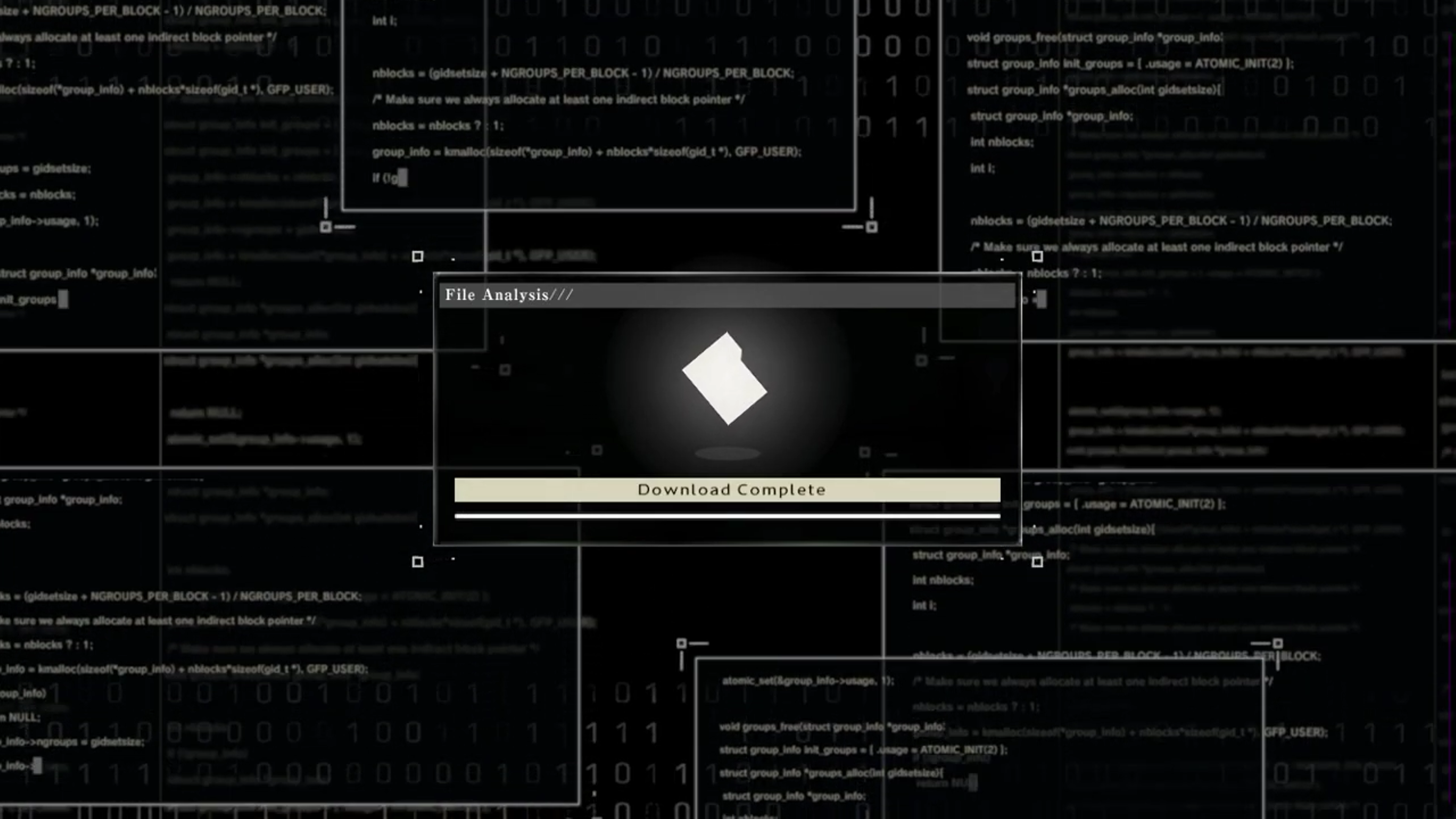












コメント